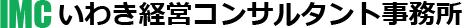ブログ
新入社員ビジネス人生いろは講;第1講:『生き甲斐』

第1話:『生き甲斐』
入社誠におめでとうございます!
いよいよ、大海原に出講ですね!?
ビジネス社会は、大変おこがましいですがそんなに甘いものではありません!
ですから、新入社員の皆さんがこれから素晴らしいビジネス人生を歩んでゆく糧となるためのお話を人生の先輩として書き綴って参ります。
どうかお付き合い下さい!
"弘法大師が詠んだ「いろは歌」を使ってビジネス社会で多くの成功体験を積むために"
こんにちは、藤本誠です。はじめまして!
有効求人倍率が上がっています。
しかし、希望と一致しないことで職を手放す人が多くいます。
自尊心にかかわることでしょうけれど、失業する辛さを最初に感じるのは収入問題ではないでしょうか?
そして、「受け入れられない自分」と向きあい始める苦痛が訪れます。
ある年齢になってリストラにあい、家族にも言えず、奥さんがいつものように作ってくれるお弁当を公園のベンチで食べる人の切迫した悲哀は、言いあらわしようがありませんね。
これから人生云々を書くことをします。
大変に生意気な試みですが、小生のライフワークの一つである「成功の研究」「夢実現」の一考をこれからシリーズでしたためたいと思っております。
この際、お大師様の「いろはづくり」ではありませんが、小生の思いつくままの『人生感』を「いろはにほへと」の順で書きます。
この原型は東京証券取引所第1部上場企業で、ますます成長中のスーパーマーケット・チェーン:株式会社H社の社内報になんともう大昔になってしまいますが、平成4年頃から、若き社員の皆さんへの先輩のメッセージとして毎月連載させていただいたものです。
それを大幅に改訂しました。
弘法大師がおつくりになられたともいう『いろは歌』、実際には作者不明です。
柿本人麻呂説もありますが、全文と現代訳は以下の通りです。
いろはろはにほへと ちりぬるを
;イロハ匂へど 散りぬるを
わかよたれそ つねならむ
;わが世誰ぞ 常ならむ
うゐのおくやま けふこえて
;有為の奥山 今日越えて
あさきゆめみし ゑひもせずん
;浅き夢見じ 酔ひもせず
「最後の一考」はかなり先になります。毎週ごらんいただく方々にとっては、気の遠くなるようなシリーズですが我慢してお読み下さい。
ビジネス人生いろは考:い;『生き甲斐』
『生き甲斐』ということばがあります。そして、「働きがい」「やりがい」ということばがその後に続くようです。
私たちはちょっと苦しいことがありますと
「もう、参った!ヤル気をなくしちまったよ!」
などと開けなおってしまうことがあります。
仕事でこういうことが何度か続きますと、今度は「働く気がしなくなった」とかなりますね。
でもよほどのことがない限り「生きる勇気もなくなった」と考える人は少ないようです。
人生って、よく考えてみますと「たった一回きり」なんですね。
その人生は誰が何と言おうと自分のものなんですね。
どう使おうが、どう生きてゆこうが、どんな人生にしてゆくのかは、本当は自分でしっかりと決めなければならないんですよね。
繰り返すようですが、ちょっと事がうまくいかないとき、たいていの人が「運が悪い」かなんとか理屈をつけてしまいます。
人のせいにする人もいますが、全くの勘違いですね。
『人生すべて自己責任』なんです。少年であろうが大人であろうが、みんな全部自己責任なのです。
ちょっと裕福になったり、楽になったりした人は「成り上がってきた過程」があり、
どうしても自惚れることもできないから「人にやさしい振り」をすることがあります。
少年に係わる何かの事件が起こったら「社会の問題」にしてしまう人がいますが、果たして、大昔からそのことが言われ解決したことがあるのでしょうか?
気が遠くなるほど解決に時間が掛かります。自分の生きている間に極楽世界・ユートピアができるのでしょうか?
他人に依存していても決して解決になりますまい。
またうまくいかないときに、しまいには「ヤル気を亡くした」と言って開け直ってしまう人もいます。
私は、「ヤル気の心を亡くす人」はみんな『忙しい人』だと思うのです。
「忙」は、読んで字のごとし「心辺に亡くす」ですよね。
余裕が無く、色々なことに気を奪われている状態です。
これから最も大切な事を、どのようにどうしてゆくか分らないことを「忙しい」というんですね。
心を亡くさないために、しっかり「自分の今」と「これから」を知っていなければなりません。
それは、自分で「感じて」、「行動して」、また、「実感する」ものなんです。
一つ一つの自ら行動した結果に対しての満足を「やりがい」というんじゃないでしょうか。
人は「やりがい」を多く体験してゆきますと、自分のこれから進むべき方向やどのようにして他人や社会に貢献してゆこうかを必ず考え始めます。
仕事をしていて、「やりがいや働きがい」は他人から与えられるもの、会社がつくるものと勘違いしている人が多いことに私はびっくりします。
会社が「労務管理」などといって、働く人のために環境整備をすることは決して悪いことではありません。
がしかし、そのことは必要条件にはなりえず十分条件にしかなりません。
会社は本当に「従業員を大切にする」と言うなら、もちろん「価値ある仕事を与える」ということはしなければなりません。
しかし、「価値ある仕事」が与えられる本人にとって「働きがい」を感じるものになるかどうかは疑問です。
実はここが重要なのです。会社は、「営利」を追求するところであり、「慈善事業」をするところではないということも理解しておかなければなりません。
ですから、従業員が与えられた仕事に「価値」を見出し、「働きがい」を感じるかどうかは実は会社の責任ではないのです!
これから少し難しいお話をするかもしれません。
あなたの手元にお茶碗があったりお箸がありますね。
いつかはこれらのお茶碗やお箸も割れたり折れたりして使えなくなります。
そのとき、お茶碗やお箸は役に立たずに死んでゆくと考えてみます。
そうすると誰かがお茶碗やお箸をつくったとき、それらは生まれてきたいってもいいのです。
生まれと死ぬまでに、お茶碗やお箸にも命があるように思います。
もちろん、それらが我々人間のように考えたりはしないでしょうが、
事実、一生を持ちます。
ほとんどのお茶碗やお箸は、その命を何に役立てるか考えてみますと、「使命」をもって一生を生かされてゆくように思います。
私たちは人間ですから、自分の一生、自分の命は「何のためにあるのか?」と考えてみるべきです。
このことについては、また後で詳しくお話をします。
「使命」を知ることや自分の命は「何のためにあるのか?」を知ることが間違いなく、 『生き甲斐』になるからです。
自分自身の人生に「使命感」を持って努力している多くの仲間がいます。
彼らは本当にすがすがしく、いつもハツラツとしております。なにかエネルギーを発散しているのがありありとわかるんですね!
彼らから教えられることがいっぱいあります。
ハタから見ていると実に忙しそうで汗水垂らして頑張っている。
なんでそこまで?と感じるものですから、素直にそのことを聞きますと『生き甲斐』だなぁ!・・・と彼らは異口同音に言います。
私がいままで彼らから教えられた「尊い人生」、『生き甲斐』をこれからご紹介し続けてゆきたいと思います。
さあ、「意義ある人生コース」にご一緒しましょう!それはあなたにとって「ビジネス成功方程式」になることは間違いありません。
またお会いできること楽しみにいたしております。
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school
飛行機の世界から学ぶ経営いろは考;第50講回最終回:『疑似相関という現象』

第50講回最終回:『疑似相関という現象』
飛行機の世界から学ぶ経営いろは考の最終回となりました。
長きに渡って、お読みいただきありがとうございました。
かなり専門用語を使った事で、抵抗をお感じになられた方も多いかと存知ます。
まず、これから述べることは「スピリチャルな世界」や、「怪奇現象」「科学で解き明かせない未知のこと」を探求する人たちを一切否定するつもりのないことをお断りさせて下さい!
私も、やくざや右翼や、もろもろその辺のチャラチャラ・チンピラという実態など怖くはありませんが、一人大きな部屋や多くの無人の部屋がある建物の夜などは・・・ビクビクしますし、少しの音も気になります(^^;
ですから、得体の知れないものに対する人間の無知なる恐怖心や好奇心を否定する人間ではありません!
もしかすると、その想像できる個人とかなり親しい方もお読みかと思いますが、勇気を持って書かせていただきます。
もちろん、このブログが原因で、Facebookやそれ以外の人間関係上のお付き合いがなくなっても仕方ないことを覚悟で書きます。
そもそも、とあるスピリチュアルな世界で教祖様的な生き方をしている御仁がいました。
一度会って、原発地域の除染に役立つ薬剤?を紹介したいということと、本当に実用化するためにいわきの放射線量の高いところで実験をやりたいので、お手伝いしてくれない
か?というものでした。
彼が、どんな仕事についているか、その時は知りませんでした。
今でも・・・皆目、解りません!
彼が、私の事務所に現れたとき、数人の中年以上の女性を3人連れて来ました。
その中の一番年配の女性が、彼のスピリチュアル集団の秘書的役割を担っているように思いました。
その女性が、おもむろに彼のことを「先生」と呼びながら、話しの前に、彼が映っているビデオを観てくれと・・・。
彼は、とある「超越なんちゃら協会」というどうみてもスピリチュアル系の団体会長なのでした。
いまグーグルで「超越なんちゃら協会」を検索しますと・・・HPが削除されています(^^;
また、「超越なんちゃら協会 詐欺」という検索結果も出てきます。
もちろん、私はその見てくれというビデオを社交実例的に観ました!
私は、彼らに分かるような顔には出しませんでしたが、本当に仰天しました!!
正直言って、笑いを消すのに必死でした(^^;
実は、その集団で教祖様的存在となっている彼が幾たびか披露する「氣の舞」と題した、太極拳なのか? なんなのか?・・・武道的な演舞もどきを見せてくれたのです。確かに、踊りとしてはまずまずのように感じました!
私は、かつて空手をやっておりました。
一応2段(現在は実力10級くらいです!)ですから、武道としての腰の座りやスタンス(脚の運び、置き方)のあり方、手足の振る舞いの基本は同じですから、彼のお遊戯の異常を発見することは簡単です!
彼の「ヘンチャラ舞」は、ド素人の方々には本物に見えるのでしょうが、私たち武道を嗜んだ者にはウソを見破ることができます。
大きなミスは、そのビデオをDVDにして置いていったのです。
私の親しくしている太極拳のかなりの上段者にそれを見せましたら、最初から顔を見合わせながら二人で大笑いしました!
合気道の師範をしている友人にも見せましたが・・・「なんじゃぁ~これは!(^^;」でした。
しかし、そのことは別にして彼が私の元に来たのは、紹介したいというその薬剤の効用を実験によって証明することが本来の目的でした。
私が、いわき市で親しくさせていただいている経営者に協力をお願いし、福島県富岡町という原発事故による帰宅困難地域(高放射線量地域)で実験をやらせていただくことができました。
お陰様で、いわき市で活躍する経営者の方のお力で、その実験を夏前から始めることができました。
そんなわけで、彼の主宰するスピリチュアルな集団が主宰する会合にも招待され、彼の熱狂的信者であろうと思われる十数人の方々(90%女性)とFacebookの友達になりました。
もちろん、彼もFacebookの友達になりました。
ところが・・・時間が経つにつれ、「科学的思考」と「健全なる懐疑心」でことを観る性格の私は、その薬剤の実験過程で・・・、どうも腑に落ちないことが多々出てきました。
決してまがい物ではないように思いましたが、3・11以降、いろいろなところで実験をやってきて、このように効果が出ていると彼が自信を持って発言するわりに・・・世に出ません!
ここでは詳細を述べることは致しませんが、私は彼となるべく疎遠になるように振る舞い始めました。
私の持つ特有な危険を感じたからです。
あの「ヘンチャラ舞」だけでなく、彼は「理学博士」を取得したというのです。
堂々と彼が教祖様をやっている集団の会合や講演会案内パンフやインターネット告知などでは、彼が出演する講演会や超なんとか気功という整体を行う会合などの紹介のときには、経歴や肩書きが明確に書かれています。
が・・・なんとその称号(名誉経営学博士???)は、全世界的に認められていないハワイにある「金銭を出せば誰でももらえる似非大学の称号」だったのです!
本来なら・・・学歴詐称か・・・、多くの人からブーイングの起こる「博士」様なのです。
確かに彼は、とある国立大学の理学部を卒業していることは事実ですが学士です。
そうこうするうちに・・・、フィリピンの大学検索では決して引っかからない・・・、へんちょこな大学で理学博士を取得し、教授であったりします。
また中小企業診断士であることも記されています。確かに30年ほど前に資格取得し、当時は通産省に登録されていたはずです。
しかし、中小企業診断士は5年に一度更新手続きをしなければ・・・中小企業診断士であり続けることはできません。
もし更新をしないで中小企業診断士でなくなっていたら、中小企業診断士を名乗ることは国家資格であることから資格称号詐称に問われます!
軽犯罪法第1条第15号では、「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」と規定されています。
この規定では、官公職や勲章、学位などを詐称したり、資格がないにもかかわらず制服や勲章を勝手に着用したりする行為が禁止されています。
たとえば博士号を持っていないにもかかわらず、「○○大学法学博士」などと名乗る場合だけでなく、単に「法学博士」と名乗るだけでもこの規定に抵触するんですよ!
このようなものはマスコミが事件性のある事案を調べるなら、すぐに裏を取ることができますが、大した事案でなければ放ったらかしですからねぇ~!
私も、もちろんそんなことをする気も、時間も、お金もありません。
大多数の人たちが、そんな面倒なことはどうでもいいのです!
それよりも・・・称号っていうのは、権威付けには持ってこいなのです!
ですから、このような手を使って権威付けをしようとする者のほとんどが詐欺師か、それに近いタイプと断言できます!
私から言わせると・・・日本のどんな小さな地方の大学や、とやかく非難される実在の大学で名実ともに確かな教授・準教授、博士号を持たれる先生に比べれてたら、とある新興国の実態があるのか?ないのか?解らないへんちょこ大学の教授であるって、よくも恥ずかしくもなく使えるなぁ~と思うのですが・・・?
彼が立ち上げた「放射能滅殺薬剤を普及する」クローズドなFacebookグループのメンバーには、例の薬剤の件で、私も登録されていたのですが、私はある時とコトを境に退会しました。
その理由は、Facebookの彼のフィードや彼の主宰する「超越なんちゃら協会」のホームページでは、平和主義者、人類の愛を説いているのに、平気でそのFacebookグループのメンバーである女性2名を排除したからです!
理由も???なのです!(詳しくは書けません! その女性に申し訳ないからです!)
一人は海外在住の女性、もう一人は彼の重要な仕事の、パートナー的存在の彼と同郷の女性でした。
簡単な理由は、その薬剤を彼らは他言する可能性があるから・・・と(^^;
それは彼の命に関わる・・・というのです(^^;
私が自らグループを退会した後、何度か彼からメッセージや電話でその理由を問われましたが・・・、のらりくらりと返事をしておりました。
ところが・・・これから書く「疑似相関」というタイトルのメルマガを読んだのでしょう!?
そのメルマガを発刊配信して1日経ったら、Facebookで彼が私を「ブロック」したのです!
おおよそ1週間後に別のタイトルでメルマガを発刊したとき、読者数が1人減っていましたから、おそらく彼は読んだのですね・・・(^^;
彼が私をブロックまでしなければならない理由は、私にも分かりません!
皆さんの推察にお任せします!
彼はいわば準宗教指導者的なスピリチュアル集団の教祖様で、講演・講義、執筆記事の端々に「愛」とか「優しさ」とか、「幸せは心の宇宙」とか、・・・、素晴らしい言葉を多用する人です。
そんな寛容なお方が・・・なぜ、私をブロックするのでしょうか・・・???
私のことをご存じの方は、これだけでも不審に思われるに違いありません!
長々と前置きをしてしまいましたが、人間の非力な精神構造を証明する一つに「疑似相関」というのがあります。
『疑似相関(Spurious correlation)』;それと同じ事が、地震予知をやっている人たちの世界でも起こっています!
「擬似相関」という精神心理について、お話をしなければないません!!
まずは、Wikipediaの定義から!
『擬似相関』(ぎじそうかん、英:Spurious correlation)は、2つの事象に因果関係がないのに、見えない要因(潜伏変数)によって因果関係がまるであるかのように推測されること。
「擬似相関」は、客観的に精査するとそれが妥当でないときにも、2つの集団間にまるで意味の有る関係が存在するような印象を与える。
2つの(確率)変数間の「擬似相関」は、第三の原因変数を導入することで生み出される。
換言すれば、AとBの間の相関を見出す。
従って、考えられる関係としては次の3つがある。
AがBを発生させるBが、Aを発生させる、またはCがAとBを発生させる最後の関係が「擬似相関」である。
そのため、「相関関係は因果関係を包含しない」とよく言われる。
なんだか、さっぱり分からない定義が書かれているようですね(^^;
もっと身近な例でお話します!
Facebookのグループ・ページの「地震の前兆」なるページが存在します。
興味本位と、もしや地震の前兆・予知について貴重な情報があるのではということで、このグループにメンバー登録しました。
数人の人は、学者の様な人で、クソが付くくらい真面目な論文やデータをアップされますが、ほとんど誰も見向きもせず、「いいね!」の数も非常に少ないのです(^^;
私は、逆にそのような数人の真面目な方の論理に興味があります。
関心の多いアップには「いいね!」はさることながら、「コメント」がズラズラとアップされます!
そのほとんどが「怖い~!(^^;」「間もなく地震が起こる!」などと、笑止千万なものが多いのです(^^;
特に面白いのは、スピリチュアル系のお人なのでしょう!?・・・「地震雲」なる写真をいっぱいアップします。
私もいささか、パイロットとして空の雲を見る事が多く、それらのアップされた写真は紛れもなく「ただの雲」が圧倒的に多いのです!
このグループ・ページに参加の信者?の多くが、『疑似相関』の呪縛に罹っているように思えます!
「地震」というあることが起こる!
そして、本当はそれとは関係のない「見たこともない現象(雲・幻覚・幻聴)]ということが起こると、「地震」と「見た雲」「起こった現象」には関係があるように見えてしまうのですね!
これを『疑似相関』と言います。
たとえば、有名な『疑似相関』の笑い話(実話)をご紹介します!
あるへなちょこ学者が、野菜の生産量と大学進学率の関係を調べていたのです。
この「仮説」自体が突飛押しもないへなちょこでしょう!?(^^;
なんとカボチャの生産量が減り、レタスの生産量が増えると、大学進学率が上昇したというです!
と言うことは・・・「カボチャを食べると頭が悪くなり、レタスを食べると頭が良くなっ
たからなのだ!」と結論づけて学会で論文発表をしてしまったのです(^^;
当然、知見ある先生方からひどくバッシングされました。
そんなことあるはずないでしょう!?
「食生活の変化」と「大学進学率の上昇」が、たまたま同じ時期に起こったというだけです!
もっとたくさんの笑い話になりそうなことが山ほど身の回りにあります!
特に「地震におびえている人」「どうしても地震が起こって欲しい人?」は、何かにつけて、まことしやかに「まもなく地震が起こる!」と信じたいし、他人をも同調させたい心理が働きます!
『疑似相関』・・・、生活場面で身の回りにたくさん起こっております!
このグループ名「地震の前兆」というタイトルに踊らされて、投稿する人が多数おり、それに同調して盛り上がりを狙う人もおります。
しかし、このグループの主宰者は純粋に今の科学では、まだ解明されていない「地震」の前兆事象があるのでは?とお考えになり立ち上げられたものだと信じております!
「あたしは『疑似相関』の自己心理が働いているのでは?」と一息呼吸をしてから、投稿なされることをお薦めしたいのですが、集団心理も働いて、我も我もでただの「飛行機雲」、「巻雲」「高積雲」「層積雲」などをアップします(^^;
ですから小生の場合は、この現象はなんでしょうか?というスタンスで、教えを請う気持ちを優先しております。
まことしやかにご自身が、地震前兆を捉まえる大家のような書き込みに対しては「アホか!」と思いますが、別段異論を書き込むことはしません!
ましてや、「いついつに地震が起こります!」なんて書き込む「ド阿呆」もいるのです!
このような人間には、不思議と信者のようなフォロワーがいまして・・もう教祖様気取りです(^^;
だいたい、見せかけのスピリチュアル系の教祖様の性格ってほとんどこんなものなのです!
(何度も念を押すようですが、スピリチュアルな世界ややっている人を否定しているのではありません!)
自身の発言にいささかの揺らぎやブレ、不安を与えることがあってはカリスマ性が保てませんから・・・、努めて「詭弁」でやり込めます。
その筋の教祖様を信じ込んだ信者の皆さんは、学歴などはまずまずなのですが、オームとまったく同様に「詭弁」にコロッといきます。
「あ~言やぁ上祐、こう言やぁ上祐!」で有名になったオームの元幹部や麻原死刑囚も、「詭弁(行き過ぎるとウソです!)」に長けていました。
書き始めに紹介したスピリチュアル系教祖様の話しをここでも出します。
彼が、信者向けに「おバカな投稿」(私の主観的感想です)をしたのです!
長文でしたが・・・
「"遠攻近交"は戦略の常識なのだ!」と書いたものですから・・・、私はすぐさま、「それは"遠交近攻”ですよね!?」って、コメントを入れて正そうとしたら・・・、「新説です!」って、コメントが帰って来た・・・(^^;
「遠交近攻」が正しく、「遠攻近交」という「交」と「攻」が逆転する言葉は存在しません!
信者様達は、絶賛・賞賛のコメントを入れています(^^;
これには驚きましたので、議論すべきでないので、「???」ってだけ、レコメントしたら・・・、5分もしないうちに買い込みが削除されているのです!
このように教祖様、カリスマ様を自認するお方達は、とにかく「謝らない!」「ミスを認めない!」のです(^^;
しかし、「おバカな教祖様」を信奉する「お阿呆な信者様達」は、教祖様のすべてを絶対に信心する(^^;
『疑似相関』的な出来事を、そのスピリチュアル系グループや新興似非宗教団体では、とにかく大事にする。
ただの「レンズ雲」でも、「彩虹」でも、エアラインの飛行機の中から見た「ブロッケン現象」にも・・・、雲の形一つにも「命名」して、大げさに感動したり、何かが起こる前兆に捉まえてしまう(^^;
時間が無駄なので私はやりませんが、上述した「地震の前兆」なるグループでの書き込みで、「いついつ地震が起こるかも!?」とか「いつまでに地震が起こっても不思議でない!」
とかの書き込みを時系列に整理して、実際に起こった地震の事実を調べればいいのですが・・・。
まずは起こっていないことの方が多いことを、統計を取ってみれば簡単に証明できます!
また、このように書くと「日本から遠く離れた地球の裏側に近いところで起こった地震」を「ほらっ! 言ったとおりだ!」と・・・抜かす御仁がいる(^^;
だから「当たった!」と、本当の日本のどこそこ地域でと書いていたクセして・・・自論を正当化するのです!
「疑似相関」それと同じ事が、地震雲や地震予知の研究の世界、スピリチュアルな世界で起こっているのです!
確かに、現代科学で解き明かす事のできない事象は無限にあります!
しかしビジネス・リーダーは、兎にも角にも「三現主義」に徹し、「現場」&「現物」&「当事者」への直接コンタクトを取り、
五感を総動員して、ことの「現象」と「原因」を突き詰めようとして下さい!
そして、多くの「情報」を「取捨選択」すべく、正しい「基準・物差し・尺度」を持って精度の高い「分析」を行い、精度の高い「仮説」を立てて「判断」「実行決断」をして下さい!
そうすれば、より精度の高い「仮説検証」ができるのです!
これを「科学的思考&試行」といいます。
勝手な「疑似相関」の「妄想」を持ってしまい、大きなバイアスを掛けてしまって、実行・実践が遅れたり、真逆に早まってしまったりすることのないようにいたしましょう!
何度も書きますが・・・、このブログの前に、メルマガとして発刊した記事を配信した途端・・・、紹介した彼からFacebook友達をブロックされました。
私は、まったくどうでもいいのですが、『疑似相関』という概念と手法が似非宗教や詐欺師の手口に意外と使われること知っていただきたいのです!
また、私たちは自分の思い込みを強くするとどうしても見えないモノを観たような錯覚、聞こえてもいないモノが聞こえているように思い込む「疑似相関」の心理的障害を抱えてしまうことを知っていただきたいのです!
あの放射能を滅殺する薬剤は、もちろん、いわき市や双葉町でクローズアップされている事実はまったく無いのが現状です!
以上、飛行機の世界から学ぶ経営いろは考全50編のおしまいです!
いつもお読み頂きありがとうございました!
いよいよ企業には、新入社員が入社してきます!
次回4月1日からは「新入社員ビジネスいろは考:全48編を逐一アップして行きたく存じます。
また、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school
飛行機の世界から学ぶ経営いろは考;第48講:『逆転層、気温の逆転層(Temperature Inversion)』

第48講:『逆転層、気温の逆転層(Temperature Inversion)』
普通は、高くなればなるほど気温が下がります。
しかし逆の現象が起こる時があります。
その逆の現象が起こっている大気の層を「逆転層(Temperature Inversion)」と言います。
「逆転層(Temperature Inversion)」では、高度が上がりますと気温が上がります!
大気の状態は極端に安定性が良くなり、大気が混ざらなくなります(上昇気流が無くなり
ます)。
冷たい空気は下がろうとし、暖かい空気は上昇しようとします。
「逆転層(Temperature Inversion)」では、上に行こうとする暖かい空気が、既に上にある
ので動きようがなく物凄く大気は安定しております。
実は問題があるのです!
大気の動きが少ないため、「霧」や「埃」が溜まりやすくなります。
視程(Visibility)が悪くなるのです!
地上付近で起こる場合は数週間も視程(Visibility)が悪い日が続く場合があります。
「逆転層(Temperature Inversion)」には大きく分けて2種類あります。
一つは地上付近で起こるものと、もう一つは上空で発生するものです。
地上付近で発生するものには、「Surface-Based」とか「Low-Level」と言われております。
夜間、風や雲がなく「放射冷却」が強い時に起こりやすくなります。
雲がない時は、地上の熱が上空に逃げていきます。そうしますと地面の温度が下がってし
まい、その周辺の大気温度が下がりるのです!
しかし上空での温度変化は少なく、「地面付近では寒く、上空は暖かい」状況になり、「逆
転層(Temperature Inversion)」が起こりやすくなります。
この状態(逆転層)で、大気の湿気が多い(Moisture Air)と放射霧(Radiation Fog)や低高
度での雲が発生しやすくなります。
飛行場周辺で、この状態になりますとVFR(有視界飛行)での飛行は厳しくなります。
なんとIFR(計器飛行)でも難しくなる場合があるそうです!
そこに強い「逆転層(Temperature Inversion)」や霧などが発生し、お昼になっても「逆転
層(Temperature Inversion)」や「霧(Fog;HazeやMistも)」などによる視程障害が残っ
てしまうことがあります。
上空で発生する「逆転層(Temperature Inversion)」は、上空に暖かい空気が流れ込んだ場
合や、下部に冷たい空気が流れ込んだ場合に想定できます。
まず考えつくのは、前線(Front)の通過時なのです!
上空で起こるものなので、流されやすく、無くなりやすいのですが、危険な状態が考えら
れるのです!
その危険な時というのは、気温が0度Cぐらいの時なのです!
この時に雨が降りますと氷雨「Freezing Rain」となるのです。
演歌ではいい歌ですが、パイロットには非常に危険な状態です!
ですから、かなりの注意が必要です。
暖かい日でも、上空に行きますと気温が急激に下がることがありますので注意が必要です!
「氷雨(Freezing Rain)」は、気温が氷点下なのに(液体の)雨が降っている危険な気象
状況のことです。
上空の「逆転層(Temperature Inversion)」で発生することがあります!
「氷雨(Freezing Rain)」の中、すなわち気温が氷点下で、飛行している航空機の機体も
0度C以下になります。その機体に雨が付着しますと、急速に水滴が凍り始めます!
これを「アイシング(Icing)」と言います。
プロ野球の投手が、投球後に肩を冷やしているのもアイシングと言いますが・・・、飛行
機のアイシングは「着氷(氷が着く)」と言う状態になります。
雪とかあられなどは、なんと一度固まってしまうと飛行機の表面にぶつかっても「アイシ
ング(Icing)」は起こりませんが、液体の状態はかなり危険です!
翼の形すらも変わりますし、飛行機の重量も急増します!
もちろん、プロペラやエンジンの空気取り入れ部分にも氷が付着してしまう可能性があり、
色々な意味で非常に危険です!
この「アイシング(Icing)」での事故は、米国では多く発生しているのだそうです。
ですから米国に訓練に行きますと失速訓練と同じくらいの頻度で「アイシング(Icing)」
除去訓練をさせられます。
「逆転層(Temperature Inversion)」の上で発生した雨や雪が、地面に向かって降ります。
雪ならば溶ける時もあります。
しかし「逆転層(Temperature Inversion)」の厚さが大きく、雨であっても、その下では気
温が氷点下以下になる時があります。
気温が氷点下になっても直ぐには、雨が雪や氷に変わるとは限りませんが・・・、気温が
氷点下以下で、液体である雨が降っている状況を「氷雨(Freezing Rain)」と言います。
周りの空気温度が氷点下以下なのに、水滴が凍っていないのような状態を「Super-cooled
Rain」とも言います。
「氷の粒、塊(Ice Pellets)」というのもあります。
上空で「氷雨(Freezing Rain)」がありますと、その気温で水滴が凍って地面まで到達す
る場合があります。
この現象を「氷の粒、塊(Ice Pellets)」と言います。
このときには、上空では「氷雨(Freezing Rain)」があると分かります。
ちなみに「雪(Snow)」というのは、水蒸気が水滴にならずに直接凍った物で、フワフワ
としています。
もう一発、「雷雨(Thunderstorm)」の内部で、水滴が上昇気流で押し上げられ、上空の冷
たい空気で凍らされた物を「雹(Hail)」と言います。
「雪(Snow)」と「雹(Hail)」は、物は同じなのですが、作られ方が違います(^-^)
皆さんがご覧になる天気図は、地上天気図というものです。
パイロットは、飛行する前に気象庁のホームページや空港の管制室から高層(上層)天気
図を入手します。
これらは、予想地上天気図、850、700hPa(ヘクトパスカル)高層天気図です。
エアーラインでは、もっと上空の天気図を入手しますが、私のような自家用パイロットは、
せいぜい富士山山頂付近(700hPaくらい)の高度以上は飛びませんから、850hPa
で十分です!
hPaは、気圧のことですから、地上付近は1000hPaくらいでしょう!?
高層天気図を読むときは、風の方向と気温がポイントです!
さてさて、またまた前段が専門的になり長くなってしまいましたが、ビジネス場面におい
て、『逆転層、気温の逆転層(Temperature Inversion)』という現象が起こることはたびた
びです。
戦いの世界では「嵐の前の静けさ」とか、「台風一過」のような安定状況ですね!
実は、ビジネス場面で、そのような状態に入った時、リスクが待ち構えているのだという
認識をビジネス・リーダーは持ち、常に「緊張感」「危機感」を持って対処しましょう!
私は経営の世界などで一流の実績を上げておられる方々とご縁を頂戴させていただいてお
ります。
彼等と真剣な語り合いをさせていいただきますと必ず共通する答えが返ってきます。
どの人もこれからの世の中がどうなるかということに、ものすごい興味を抱いております。
その興味で先々を見てゆきますと、どうしても
「このままでいいんだろうか?」
「これから、こんなことをしていてはダメだなんだよなぁ~!」
といった『危機感』をいっぱい口に出されます。
「こうあるべきだ!」などという、まさに評論家タイプ発言でないのが実務家の一流人の
言葉であることに気づきます。
この『危機感』が、彼等にとって次に『緊張感』をもたらします。
それが、普通の人とは違う物事に対する真剣な取組み態度となって顕れます。
そしてますます、取組みの精神的緊張度が高じてきますと『集中力』が湧いてきます。
専門家はこの状態の脳波がα波だと言います。
このα波を外から入れようと、変な機械を購入する者がいます。
若い方々にはおわかりにならないでしょうが・・・その最も有名なアホなことやってたの
がオーム真理教のヘッドギアではないでしょうか?
もしくは、耳からα波を促す周波数の音を入れれば同じ様な効果があるんだと言って機器
を売っている人もいます。
この機器の推薦人にコンサルタント会社を日本で唯一上場させたと自慢している、そして
巧みな出版をすることで有名なコンサルタントがいます。
不思議なことに、このコンサルタントの推薦するいろいろな発明紛いのものが急速に普及
することがなかなかありません。
本来「本物」と言うのは、コマーシャルをしなくても爆発的にクチコミによって広がるも
のです。
大変に大それた言い方をしますが、大学受験用・資格試験合格用に売り出されていました
あんなもの(ヘッドギア、α波促進音響装置)で集中力が湧くんなら、受験生は誰でも東
大クラスの大学に行けるし、司法試験も簡単に受かりますよね!?
しかし絶対そんなことは起こりません!
ということは、あれは”ハッタリ”であると気付かねばなりません。
まったくオームの連中と比べて五十歩百歩なのです。
注意して下さい!
やはり『集中力』を誘発させるのは本人の『真剣さ』、すなわち『緊張感』にほかなりま
せん。
この『緊張感』は、常に今の環境と自分の状態を素直に対比させることです!
そして「このままではイカン!」と自身に言い聞かせる姿勢が芽生えてきます。
これを『危機感』というようにします。
『危機感』は、全身をものすごく「敏感」にさせます。
目に見えないアンテナを体のあちこちに張りめぐらします。
どんな些細な事も取り込もうとします。
それが「ボキャボラリ」として、たぶん脳だろうとは思うのですが蓄積されてゆきます。
潜在意識のすばらしいところなのですが、真剣な物事への取組みによって365日24時
間寝ていても思考を補完してくれます。
突然に、閃くことがあります。
不思議と、そのときは大変に心地好いものです。おそらく「悟り」というのがそんな境地
じゃないかと思ったりします。
ですから閃く経験をした人は、もう一度、同じ快感を味わいたくなるのではないでしょうか?
お釈迦様が出家を決意したは、自分のエゴでの解脱を目的にしたのではなく、衆生の救済
について『危機感』を感じたからと私は信じております。
お釈迦さまが涅槃に入られてから後、何百年もの間、小乗(自分だけの悟りを目的とする
教え)でしたが、脈々と流れるお釈迦様の本心は発現して現在に至っていると信じており
ます。
ですからオームの誰かさんとは発心がまるで違う訳です。
さあ、ぜひ自分の身の回りの環境を真剣に考え、これからの自身の身の振り方を想って
下さい。
そして、一流人との触合える所まで一緒に行きませんか。
一流人には、ちょっとした努力で成ることができます!
それは、『危機感』と『緊張感』と『向上心』が芽生えた時です。
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school
飛行機の世界から学ぶ経営いろは考;第49講:『雷雨、雷雲(Thunderstorm)という現象』

第49講:『雷雨、雷雲(Thunderstorm)という現象』
今回は、前回書き切れなかった続きとさせていただきます!
「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」は大気の対流によって発生します。
不安定(Unstable)な大気の代表例なんですね!
大気の熱が上昇することを上昇気流(Convective Current、もしくはConvection)と言います。
小さな規模の上昇気流(Convective Current)はあちこちで発生しております。
どでかい上昇気流(Convective Current)が「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」です。
どのような現象なのか?
典型的な例ですが、昼間、太陽の直射日光で地面が熱せられ発生します。
地面付近に存在する湿った空気が、地面の熱で暖められ上昇して発生するわけです。
上空にある大気は地面の熱では温められることがありません!
そのため、暖められた上昇気流と上空の大気との温度差が大きくなり、大気がもの凄く
不安定になってしまいます。
温度差が大きければ大きいほど上昇(対流)も強くなり、「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」
が発生しやすくなります。
地面の加熱だけが原因ではありません。
テレビの天気予報でよく気象予報士が「上空に冷たい寒気が入り込んで・・・」と言います。
このような状態でも同じ「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」が発生する条件を作ります。
上に冷たい物が入り込むということは、下の方が暖かいという訳ですから、その境目に
対流が起こります。
多くの場合、前線付近で暖かい大気が冷たい空気の下に入り込んでも同じ事が起こりやす
くなります。
前線では初めから雲が多いので、「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」が発生しても見えない事
があります。
この「見えない雷雨」のことを英語では「Embedded Thunderstorm」とも言います。
小型機では、あまりにの高価なので気象レーダーを登載していませんから、飛行前に天気
図を見て、前線付近に向かうようでしたら緊張するくらい???注意が必要です!!
有視界飛行(VFR:Visual Flight Rule)でも、この雲の下は気流の乱れが大きくて危険で
す。
強烈な「ウィンド・シアー(Wind-Shear)」が頻繁にあります。
旅客機でも、下降気流で離着陸時に地面に叩き付けられる時もあるぐらいですので、「雷
雨、雷雲(Thunderstorm)」が予報されている時は飛行を取り止めるか、数時間待つこと
が不可欠です!
私の経験では、1時間程我慢するだけでかなり状況が良くなることがありました。
「スコールライン雷雨:Squal Line Thunderstorm」というのが、もっとも危険な状態の「雷
雨、雷雲(Thunderstorm)」です!
前線性ではないのですが、複数の「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」が並んでいる状態です。
これは最も威力が強くて、「雹、氷の塊(Hail)」「竜巻(Tornado)」「猛烈な乱気流」「強
烈な雨」などが混在します。
特に起こり易いところは、「寒冷前線」の前方です。
「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」の時には、「ひょう(Hail)」が発生します!
「ひょう(Hail)」とは、「氷の塊」のことです。
雲の中で発生した雨の粒(液体)が上昇気流で上の方に持って行かれ、他からのモノと
合流しで大きくなった液体が途中で凍ってしまった状態です。
地表に向かって落ちて行きますが、途中で溶ければ単なる雨となります。
凍ったまんま、地面に到達しますと「ひょう(Hail)」と呼ばれます。
上空で「ひょう(Hail)」に遭遇しますと、機体に穴を開けたりする時があります!
だって石が飛び交う中に、飛行機が時速100~300キロで飛んでいると想像して下さ
い・・・(^^;
実はこれは知っていてお得情報です(^^♪
上昇気流がどんなに強烈であっても、大気の状態が物凄く不安定でも、「逆転層
(Temperauture Inversion)」が強くても、物凄く強い前線や低気圧があっても・・・、
実は大気に「湿気、水蒸気、水(Moisture)」がなければ雲はできません!
もちろん「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」もできません!
雨は、もちろん絶対に降りません!
強烈な乱気流の可能性はありますが、大気に十分な「湿気、水蒸気、水(Moisture)」が
なければ雲やヒョウやアラレの現象は発生しません(^^♪
空気がカラカラに乾いている砂漠地帯や、私の知っているところでは、米国西海岸などで
は強烈な上昇気流があっても雲が出来ません!
日本だと、湿気が多くて夕立になりますね!?
とにかく、これは十分な湿気があるからなのです。
多くの気象現象は、この「湿気(Moisture)」の存在が必要なのです!
ですから「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」発生の必要条件は、多くの湿気があることです!
「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」が起こるための条件があります。
その条件は、始めに何らかの理由で大気が不安定になることです!
直射日光もあれば、大気の移動などが考えられます。
その不安定さが「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」の元なる「上昇気流や対流(Updraft and
Convection)」を作り出します。
もう一つの条件として湿気が必要です。
湿気がなければ雲すら出来ません!
なんどもくどく書くようですが、大気がかなり不安定で、上昇気流があっても、湿気がな
ければ乱気流が起こるだけです!
「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」発生に必要な条件は、
1)不安定な大気 ⇒ 上昇気流が発生しやすい状況 ⇒ 大量の空気と湿気を上に持ち
上げる
2)十分な湿気:無ければただの乱気流だけ・・・
3)「気温低減率(Lapse Rate)」が大きいこと!
高度に比例して大きい気温差が強いと上昇気流を生みます。
「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」のライフスタイルは、3つのステージとして次の物が
あります。
1)「積雲ステージ(Cumulus Stage)」:出来始めの状態
2)「成熟期(Mature Stage)」:地面に雨が降り出す状態で最も危険
3)「放散ステージ(Dissioating Stage)」:終焉と言いますか、最後の形ですね!?
1)「積雲ステージ(Cumulus Stage)」:乱雲が生まれる状態とだんだんと発達状態です。
上昇気流ばかりで、雲がグーンと上に伸びていきます。
上空では気温が低いので、水滴がドンドンと溜まってきます。
最初は雲だけですが、途中から雨や雪の状態になります。
しかし雨ができても上昇気流が強いので下に降らず、上昇風によって上空へ押し上
げられます。
あの「入道雲(Towering Cumulus)」が代表的な雲ですね。
上昇気流の強さと雨や雪の重さのバランスが崩れるまで、上昇気流とこの「積雲ステ
ージ(Cumulus Stage)」は続きます。
2)「成熟期(Mature Stage)」:地面に雨が降ってくる状態です。
最も威力の強いステージなのです!
雨が降る段階ですから「Cumulo-nimbus(積乱雲)」と言います。
上昇気流によって、上へ上へと押し上げられた雨や雪は、気温の低下と共に大きくな
ります。
しかし上昇気流にも限界があります。
雨などの重さが上昇気流よる力よりも大きくなりますと、今度はその雨などが一気に
下に落っこちる訳です! 結果、地上に雨をもたらします。
その時、水滴(雨)には摩擦抵抗がありますから、周囲にある空気までも下に引き
ずり落とします。
そして、その下に行く力が「下降気流(Downdraft)」を発生させます。
「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」の「成熟期(Mature Stage)」の中では、上昇気流と
下降気流がランダムに多発しますから、強い乱気流やウィンド・シアーが発生する
訳です!
それが余りにも強すぎますから、まともにその境目に遭遇しますと、どんな航空機(飛行機)
も、ほぼ間違いなく破壊されてしまう危険性があります。
また、この上昇気流と下降気流での境目では空気が強烈に擦れ合うので、大量の静電
気が発生します。
その静電気や地面と雲の電極の差などで「稲妻(Lightning)」が発生します。
この時に発生する音が「ゴロゴロ」と言う雷鳴です。英語では「Thunder」と言い
ます。
この「稲妻(Lightning)」が「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」の最大の特徴です。
「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」と言うには、この「稲妻(Lightning)」がなければ
なりません!
成長して重くなった「霰:あられ(Hail)」は下に落ちますが、軽い「氷晶(ice crystals)」
は上に持ち上げられます。
なんと「霰(Hail)」は負の電荷、「氷晶(ice crystals)」は正の電荷に帯電するのです!
雲の上層には正の電荷が蓄積され、下層には負の電荷が蓄積されますから・・・、
雷様は、基本的には上から下に落っこちます(^-^)
横に雷様が走るのは、落ちる「霰(Hail)」の外側にできつつある「氷晶(ice crystals)」
が水平線上に存在したときです。
「成熟期(Mature Stage)」は地面に雨が落ちてきて、下降気流と上昇気流が同時に
あり、威力が最大となり、乱気流が最も強く、非常に危険なのです!
上下の違いがあるのは「ハサミ」の原理と同じです!
「積雲ステージ(Cumulus Stage)」では上昇気流だけなのですが、「成熟期(Mature Stage)」
では、その上昇気流に下降気流も混ざり、乱気流の威力は「Cumulo-nimbus(積乱雲)」
の中でも最強となります!
「Cumulo-nimbus(積乱雲)」の雲の下ではウィンド・シアーがありますので、有視界
飛行(VFR)であっても絶対に危険です!
もちろん「積雲ステージ(Cumulus Stage)」でも「入道雲(Towering Cumulus)」が
ニョキニョキ段階でも強い上昇気流がありますから、乱気流は強いのですが、まだ
下降気流がないので、「成熟期(Mature Stage)」の「Cumulo-nimbus(積乱雲)」
よりかは、威力は若干弱いですが危険には変わりません!
「積雲ステージ(Cumulus Stage)」でも、たまに急激な下降気流が生まれたりします。
それが「マイクロ・バースト(Microburst)」と呼ばれる現象です。
非常にく限られた範囲で、強烈な下降気流が落ちてくる様な現象だそうです!
地面にぶつかりますと、猛烈な風が外側に向かって発生します。
その時に、飛行機が通過しますと急激な速度変化が発生し、旅客機でも墜落するそう
です!
3)「放散ステージ(Dissioating Stage)」:「下降気流(Downdraft)」が中心になります。
これは終わりに近づいている状態です。
どんなに強い「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」でも、最後は威力がなくなります。
上昇気流がなくなってきますと当然のことながら威力が弱くなっていきます。
まだ一部では少しだけ上昇気流が残っていることもありますので、ゴロゴロ言う時が
あっても量は減っていきます。
今回のビジネス・リーダーへの教訓は、「会社の寿命(ライフ・サイクル)」ついて、
お話します。
「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」のライフ・サイクルがあるんだということを理解しま
しょう!
会社・製品・サービスには、生けとし生けるモノ(人間や生きモノ)と同様に、その誕生
から衰退までの寿命があります。
これを「ライフ・サイクル」と呼びます。
一般的に、「導入期」 ⇒ 「成長期」 ⇒ 「成熟期」 ⇒ 「衰退期」があります。
昨今、このサイクルの期間がどんどん短くなってきています!
この事実を無視して、というより事実を認めたくなく目を背ける精神構造がビジネス・
リーダーにはあるということを自覚すべきです!
企業、製品、商品、サービスは、「必ず売れなくなる時期が来る!」という事実です!
「いや!そんなことはない! 我が社の製品・商品・サービスは業界一なんだから!」と
思いきや・・・「シャープ」はあっという間に沈没しましたよ!(^^;
そのことを自覚しないと後々、致命的な問題を引き起こすことになります!
現在、我が社は、我が社の製品・商品・サービスが、ライフ・サイクル上のどのステージ
にあるかを把握しておかねばならないのです!
我が社が成長・発展していくためには、今後、どのような手を打つべきかの「戦略」を
常に検討しておくべきなのです。
「経営計画」「事業計画」を策定したが、その通り企業を成長・発展させていくところも
あれば、残念ながら未達成に終わってしまうところもたくさんあります。
その違いは?
企業・組織、製品・商品・サービスのライフサイクル上の「成長ステージ」を無視した
計画を策定していまうことが最大の原因です!
「製品のライフ・サイクル」をご存じの方は多いと思います。
一般的に「4つの段階」に区分されています。
「導入期」 ⇒ 「成長期」 ⇒ 「成熟期」 ⇒ 「衰退期」
です。
それぞれの段階に、以下のような特徴があります。
1)導入期
製品を市場に投入し、販売量・販売金額が緩やかに伸び始める時期です。
売上を高めるには、まず市場での認知度を高める必要があります。
2)成長期
製品が、市場で受け入れられますと販売量・販売金額とも順調に伸びます。
その伸びは、驚くほどと言っていいでしょう!
「有頂天」になる直前時期ですね!?
この段階で、着実に「生き残る」ためには、「マーケットシェア」を「最大化」する
ことが必要不可欠なのです!
3)成熟期
販売量・販売金額が安定してきますが、伸びは鈍化します。
横ばい状態を辿る時期ですね!?
製品・商品の普及率はほぼ限界に達します。いわば「飽和状態」に達します。
「頂点」に達した思うべきです!
「頂点」が「有る」から「有頂天」なのです!
このまま手をこまねいていますと・・・「奈落の底に真っ逆さま」は必然なのです!
4)衰退期
販売量・金額とも需要が減退し、落ち込んでくる時期です。
状況に応じて、勇気を持って「撤退」を検討する必要が出てきます。
「引き際」が重要なのです!
以上のライフ・サイクル論は、一般的に誰もが知っているものです。
ここに
5)思い切った「事業転換期」
を加えるのです!
この「事業転換期」は、3)成熟期に決断することを強くお勧めします。
いわば「第2の創業」であったり、再度、足下を固める意味での「事業ビジョン」の策定
時期なのです!
この「事業転換期」に、再度、創業したころのことを思いだし、より深い次のステップを
踏んで対策を講じることを強くお勧めします!
1)「開墾」ステップ:市場調査や人員戦略が中心の時期です!
とにかく、市場調査を綿密に行い「需要」を掘り起こします。そのためにも、その
後のためにも組織人員の異動も含めた戦略を策定すべきです!
2)「種付」ステップ:営業や宣伝活動が中心の時期です!
とことん、営業に特化し、思い切ったプロモーション(広告宣伝)活動を人海戦術
で行うのです!
3)「開花ステップ」:営業や宣伝の効果が現れる時期です。
しっかりと「実を結ぶ」ために、肥やしをやり、水を切らさないことです!
4)「結実」ステップ:開花の結果は、とりもなおさず契約に結びつく時期です。
販売がいよいよ順調に進む時期です。
組織ムードも高めることです!
5)「収穫」ステップ:売上げが継続し、利益回収される時期です!
ここで散財は厳禁です! 「ダム経営」に徹するために、利益を次の再循環のために
利益蓄積すべき時期です!
6)「休息」ステップ:事業を休むことではありませんが、いままでステップの反省を
しっかり行うのです!そして、今後の指針を再度明確にすべき時期です!
企業・組織も農産物とまったく同様に、耕して、種を蒔き、四季に応じた手入れをシッカ
リすることによって、収穫期に豊かな実りをもたらしてくれるのです!
雑草が生えているのに、それらを抜かず、水をやり過ぎたり、肥料をやらなかったりすれ
ば、植物は収穫を迎える前に枯れてしまいますね!?
企業・組織にも、人生にも「四季」があります。
「冬」の次には、必ず「春」あります。「春」の後には「夏」が・・・。
「夏」の後には必ず「秋」が・・・。
これが「自然の理」なのです!
その四季折々に為すべきことをするのです。
決して、四季が逆転・スキップ現象を起こすことはありません!
ところで・・・「STAP細胞」はどうなったのかな?・・・関係ないか!?(^^♪
再度、ビジネス・リーダーの皆さんは、自社組織の「ステージ」を『脚下照顧』してみて
下さい!
ここで一旦、パイロット・ビジネスいろは考は書き止めします。
これからいよいよ新入社員が企業・組織に入社してきます。
ウィーク・デーにはしばらく毎日、「新社会人の皆さんへ! 人生いろは考」をアップ
することにいたします。
パイロット・ビジネスいろは考は、その後、まだまだ続けてゆきます。
休止中に、FAAのパイロット関連の書物の翻訳・解読・理解を深めておきます!
乞うご期待(^^♪
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school
飛行機の世界から学ぶ経営いろは考;第47講:『雷雨、雷雲(Thunderstorm)』

飛行機の世界から学ぶ経営いろは考;第47講:『雷雨、雷雲(Thunderstorm)』
航空英語試験と言うのがあります。
もちろん私は受験しておりませんが、エアーラインのパイロットや欧米で飛行訓練をする
場合、この認定試験に合格していないとダメなんですね!
そんなに難しいとは思いませんが、口頭試験が難しいようです。
あるカード(飛行場などの状況イラストが描かれている)を見せられて、その状況を英語
で試験官に説明します。
その後、試験官から、このような状況の場合、あなたが機長ならどのように判断するか?
っていう質問がきます!(実際の過去の試験問題)
私も少し勉強しましたが、最初に出くわしたカードは、飛行場周辺が真っ暗になっており、
周囲でゴロゴロ・ピカピカと雷様が雄叫びを上げています。
複数の滑走路や出発直前ライン、タキシーウェイ(誘導路)、ピットにも多くの旅客機が
描かれています。
この状況を英語で説明したら、あなたはピットにいる航空機の機長だけれど、このあとど
うする?ってな質問があります。
もちろん答えは一つ!・・・「待機します!」
そうしますと、「なぜですか?」てな質問が返ってくるわけです。
航空英語試験は、ただ英語が話せるだけでなく、今までブログを書いてきた航空機・飛行
機に関連する総合知識がないと答えられないのです!
FAA(米国航空協会)のパイロット免許を取得するなら、試験官から根堀葉堀と英語で
質問を受けますので大丈夫ですが、日本で免許を取りますと日本語ですから・・・欧米(海
外)では、通用しないのです。
そのため国際線のパイロットや欧米で自由に飛び回りたい人は、航空英語の認定資格がな
いと飛ばせてくれません。
さて前段が長くなってしまいました。
実は、雷様のことを書くのも長文となります。
執筆能力、説明能力が脆弱であることはお許し下さい!
今日のブログは長文です!
「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」というのは、「Cumulonimbus」と言う雲のことです。
簡単に言いますと「かみなり雲」です(^^♪
物凄く強烈な乱気流や雨、稲妻などが発生し、航空機・飛行機にとっては物凄く危険な
気象現象です!
ピカッと光る物が「稲妻(Lightning)」です。
稲妻の方が強烈な響きですね!?
ゴロゴロと鳴る音を「雷,雷鳴(Thunder)」と呼びます。
この「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」は、極度の危険を表すモノだと・・・訓練生の時に
はくどいほど教官から教わります。
飛行機に乗る者は、絶対に近づくことを避けるべきです!
そこには多くの「乱気流(Turbulence)」や「ウインド・シェアー(Windshear)」が存在し、
最大になります。
大型機でも、ジェット戦闘機でも、まともにそこに入れば空中分解もあります!
絶対に近づいてはなりません!
雲の中だけなく、この雲の下も物凄い乱気流や大雨、竜巻、落雷などありとにかく凄く
危険なのです!!
「Cumulonimbus」というのは、おなじみの「積乱雲・入道雲」のことです。
「Cumulo-」「Cumulus」と言うのは「積雲」という意味です。
上にモコモコと発達する雲のことです。
「Nimbus」とは「雨雲」のことで、雨や雪をもたらす雲の事を言います。
「Cumulonimbus(積乱雲・入道雲)」は強烈な上昇気流が発生し、地上や水上から大量の
水蒸気を吸い上げます。
雲自体が、どんどん水分を増やし重たくなります。
結局、持ちこたえられなくなって冷やされた水蒸気が雨、「雹(ヒョウ)・霰(あられ);Hail」
などになって落下します。
その時、強い下降気流が発生します。
上昇気流と下降気流との境目が発生します。
この境目で、強烈な摩擦現象が発生します。
そして静電気が溜まります。
ついには放電し、「稲妻・雷(Lightning)」となり、ピカピカ・ドンドン・ドッヒャーンと
空気を振動させます。
それが「雷鳴(Thunder)」となり大きな、驚くほどの音となります!!
この稲妻が「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」の特徴です!
一般的には強烈な雨が降る時が多いですが、気象条件によって地面に到達する前に蒸発し
て「尾流雲(Virga)」と呼ばれる現象が起こったりします。
「尾流雲(Virga)」というのは、多くの雲種にみられる雲の変種の一つです。雲の高度に
かかわらず、雲から大量の雲粒が落下すれば見られます。巻積雲、高積雲、高層雲、層積
雲、積乱雲、積雲、乱層雲の計7種に見られる現象です。
雲の下から筋状や柱状の白っぽい霧のようなものが垂れ下がったように見えます。
とにかく「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」では必ず発生している現象が「稲妻・雷(Lightning)」
と強烈な「乱気流(Turbulence)」です!
飛行機を設計する時には、「乱気流(Turbulence)」による影響も考えて設計していますが、
その予測数値よりもダントツにどでかいのが「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」です!
AIM(Aironautical Information Manual;航空情報マニュアル)では、「雷雨、雷雲
(Thunderstorm)」から最低でも20マイル以上(30km以上)は離れることを推奨し
ています。
「雹(ヒョウ)・霰(あられ);Hail」は氷の塊です。
高速で飛行する飛行機にとって非常に危険です!
速度が速いので、飛行機に穴を開けることぐらいは簡単にやっちゃいます(^^;
また強烈な上昇気流が大気を上に押し上げますので、液体状態の雨水も氷点下(Freezing
Level)以上になります。そうしますと、「超冷却水:Supercooled Water」という状態にな
りやすく、水滴が大きい時に発生しやすい危険なIcing・着氷である「Clear Icing状態」の
危険も高くなります!
また雷雲の周辺りでは、「竜巻(Torrnado)」が発生したり、「マイクロ・バースト(Micro burst)
と呼ばれる強烈な下降気流が発生します。
雲の中だけでなく「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」の周辺でも危険な状態が、いつ発生し
ても不思議ではないのです!
「稲妻(Lightning)」は、それほど危険とはされていませんが、飛行機に穴を開けたり、
電気系統や磁器類(コンパス等)を狂わせたりします!
それと、私は経験がないのですが、眩しいのでパイロット目にも危険となるそうです!
大きい稲妻のが目の前に来ると一時的に視力が無くなったり、失明することもあるそうです。
また稀に燃料を引火させたりすることもあるそうです!
とにもかくにも・・・「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」や「台風(typhoon)」は、自然の
驚異です!
私たち人間の知識では計り知れない、想像を超える自然現象です!
絶対に無理はしないことが、生命を守ります!
「雷雨、雷雲(Thunderstorm)」は殺傷能力が強いので慎重に対応しなさい!とAIMに
は書いてありますが、生還した人が書いたのか?疑問です。
とにかく緊急措置として、
・間違って入ってしまった場合、計器を見ることとあります。
(外部を見ると稲妻で、目が見えなくなる可能性が高くなる)
・エンジンを減速した時の設定にし、その後はエンジン設定を変えないこと。
・水平飛行を保つ様にするが、無理して高度は守らない。
・入ってしまえば、真っ直ぐと突っ切る方が早く貫通できる場合が多い。
・旋回するとLoad Factor(G、ストレス)が増すので避けること。
そんなこと書いてあったって、生還できるかどうか分かんないんだから・・・「君子、危
うきに近寄らず!」なんです(^-^)
この続きがあるのですが、これ以上書いたら、まったく読んでいただけなくなるでしょう
から、ビジネス・リーダーへの教訓に入ります。
今回は、「氣」について書かせていただきます。
「氣」というのは、何かに対して向けることができます!
内向的に・・・自分自身の方に向けることもできますが、外部に向けて発することもでき
ます!
内に向けても、外に向けても、鍵となることは、自身の「心」も対象の方向に向きます!
「氣」を向けるときには、身体も対象の方に向け、しっかりした正しい態勢を取ることが
肝心です!
悪い例を挙げてみましょう!
例えば、テレビを視ながら勉強する。
スマホを触りながら食事する。
どちらも身体は勉強や食事の姿勢を取っているものの、心はテレビやスマホという別対象
に向かっています。
実は、これでは自分自身の最高のパフォーマンスを出すことはできません!
また、食事を共にしている家族や友人にも良い印象を与えませんねね!?
おそらく、彼らは自分をあなたから大切にされているとは思わないでしょう!?
正しい態勢というのは、「身」も「心」も対象にすべてが向かっている状態を言います。
まずは、身体を整えましょう!
肩の力を抜きましょう!
重力を感じるように自然に立ってみましょう!
今の「心」を100%対象に向けるように意識してみましょう!
その時、身体を物理的にそちらに向けることが肝心です!
まずは視線を対象に向けて動かしましょう!
身体も対象に正対させ、・・・その対象に没入してゆく気分を持ちましょう!
ビジネス・リーダーなら、部下から仕事上の相談を受けることが多いですね!?
部下の話を一所懸命に聞くのです!
それ以外のことは一切しないことです。
部下からどのように思われているか?などと上司としての評価のことも考えないことです。
部下の精神的状態を真剣に観察しましょう!
彼(彼女)は肩に力は入っているか? 呼吸は一定か? 表情は豊かか?
このような観察をしておりますと、このチャンスの活かし方(意味)を考えるのです。
「方法論」を伝えるべきか? 「心構え」を問うべきか? 「一緒に」、一つの解法を
実践すべきか?
なるべくなら、・・・時間の猶予があれば、自分自身の「身」も「心」も、部下のそれと
「一致」するようなしてみようとして下さい!
既におわかりの人もいるかと思いますが、「身体」と「心」が対象に100%向いていま
すと、「時」と「場」も100%が対象と共に在るわけです。
「身体」と「心」と「時」と「場」を100%揃えることができたなら、あなたの「感度」
は飛躍的に高まります!
インディアンと藤本・・・ウソつかない!(^^♪
その時、「氣」が満ち溢れる瞬間なのです。
もしや、非常にスピリチュアルな表現を使っているかも知れませんが、「対象」に「自分
自身(自己)」を「投影」しますと、自分自身の「身体」が、「喜び」や、逆に「痛み」
を感じることがあります!
こんなとき、「当事者意識」が溢れ出てきて「インスピレーション」が生まれます!
どんどん、それが質的にも良いように拡大して、新たな意味を発見することが多々ありま
す。
これこそ「アイデア」と言っていいのではないでしょうか?
ぜひ、真正面に立ち向かった「氣」の入れ方、使い方をなされてみて下さい!
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school