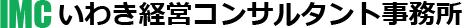ブログ
新入ビジネスリーダーいろは講;第12講:『5W2H』と『意見』

第12講:『5W2H』と『意見』
~弘法大師が詠んだ「いろは歌」を使ってビジネス社会で多くの成功体験を積むために~
いろは
いろはにほへと ちりぬるを
;イロハ匂へど 散りぬるを
わかよたれそ つねならむ
;わが世誰ぞ 常ならむ
うゐのおくやま けふこえて
;有為の奥山 今日越えて
あさきゆめみし ゑひもせずん
;浅き夢見じ 酔ひもせず
の「を」、この字ではじまる日本文字はありませんので、横文字で代用させてもらいます。
ワープロ・ローマ字打ちの【ヲ】は「W」+「O」なのですね。
【W】は、5W2Hの「W」、【O】は、オピニオンの「O」にします。
オピニオンとは意見のことです。
「いつ」+「意見」を述べるのか!?
「どこで」+「意見」を述べるのか!?
「だれが、だれに」+「意見」を述べるのか!?
「なにを、なんの」+「意見」を述べるのか!?
「なぜ」+「意見」を述べるのか!?
さあどうですか、・・・皆さん!?
『意見』を述べるという機会がどれくらいありますか?
多分その逆の方が多いのではないでしょうか・・・。
特に、組織に入ってみますと上司や先輩が多くて、好き勝手な『意見』は、勝手放題には言えませんよね!?
「何か、意見を述べてください!」
と言われてみたところで、なかなか言えません。
しかし、『意見』を述べるということは非常に重要なのですね。
精神衛生上、思っていることを口に出さないで思っていることを出し押さえていますとフラストレーションというイライラがたまり、本当に病気になる人が出てくるのですね。
たとえば・・・、
「あなたの意見は間違っている!」とか、
「あなたの意見はおかしい!」
などと言われることがありますよね!?
特に日本人は、そのような言われ方をしますと自分の「全人格」まで否定された気分になるようなのですね・・・(^^;
そんなものですから・・・、そのように言われたくない。
だからあまり余計なことは言わない、ナアナアの妥協がはじまるのです。
「男は黙って、サッポロビール」ってCMが昔にあったのも、日本男児の意気込み、威厳を表現するために作られたものでした。
でも当時は、あのCMを観た人たちが一様にビールが飲みたくなっても、キリンビールを買った。
他社のCMのおかげでキリンビールが売れたという笑い話がありますが・・・ここでは関係ないかぁ(^^;
いまは、アサヒビールがシェアー一番なんですから・・・世の中、捨てたモノではありませんね!?
欧米人はぜんぜんそんなところがないですから、ディベート(討論、議論)が盛んになのです!
また「イエス」「ノー」をハッキリ言うことも小さい頃から躾けられていますから、「意見」を堂々と言います。
『意見』というのは、いままで生きてきた多くの経験の組合わせなのです。
ですから経験が増えて、その組合わせのための価値観が変化しますとコロッと『意見』が変わってしまうことがあります。
そのことを恥かしがることはまったくありません!
むしろ、かたくなに『意見』を変えないガチガチの方が恥ずかしい考えだと私は思います。
『意見』を出して、その「反応」から確信を持ったり、「反論」から疑問と再考が生まれます。
良い会社や組織では『議論』を活発に行っています!
ですから一方的な伝達や上司の押しつけだけの変な会議はしません。
みんなが『意見』を徹底してぶつけ合うのですね。
そして、出される『意見』について、お互いにそれを尊重し合うのです。
礼儀作法を知る仲間は、「朝までテレビ」や「TVタックル」(最近はなくなったようですが・・・)の様に、相手の意見も最後まで聞かず、自分の主張だけほざく様な恥ずかしいことはしません!
みんな良く『意見』に傾聴します。
それに対してまた、『意見』が出てくる訳です。
だから、はたからみているとその会議は実に活発、元気に見えるのです。
もちろん、よい『意見』が取入れられるのですから、うまくいくことが多くなるのです!
業績はおのずと向上します!
家庭でも同じですね。
文句ではなく『意見』の出る家庭は明るいですね。
「こうしたら、いいんじゃないだろうか!?」
「こうするほうが、このようにうまくいくんじゃないでしょうか!?」
というのが『意見』なのです。
「いままで、こうしてきたんだから・・・」
「めんどくさいよぉ~」
というのは『言い訳』といって『意見』ではないのです!
『言い訳』は悪魔の誘いといいまして、自分をどんどん悪くしてゆくものです。
なぜなら、もっとも非生産的だからなのです!
『意見』は世の中を変えるものなのです!
プラス思考の行為なのです。
『意見』の言える環境をつくるには、上司、先輩の技量が大切になってきます。
それは特に新人である人の『意見』を聴く、『小数意見』を尊重し、十分に真意を聴こうとすることですね。
「いつでも、どこでも、だれと」でも『意見』をぶつけあうことは、あなたにとってすばらしい人生を創って行くものです。
多くの人脈づくりにもなります。
「なにか、意見はありませんか?」
「はい!・・・店長!、わたしの意見を聴いて下さい! わたしの意見には自信があります! どうか、よろしくお願いします!」
あれっ、どこかでやったなあ・・・!?
そうなのですね、私の主催する新人研修の男子行動訓練では「敵陣突破訓練」というのを行います、
これも教官に「よぉ~しっ! 合格!」って言わせるまで、「私の意見を聞いて下さい!」を連呼し続けますね!?
合格の基準は、あなたが教官になると判ります!
本気で、自分の意見を聞いて貰いたい情熱を持ったら、確実に言動が本物になります。
日頃の仕事の中でも、ぜひ『意見』を積極的に言う訓練をしましょう。『意見』を言うために、多くの言葉を使うようになります。言葉には『言霊(ことだま)』といいまして「魂」が宿っているそうなのです。
言葉を使う事ことによって「言葉の魂」が喜ぶのですね!
その「魂」が、いろいろ面倒をみてくれることがあるもですね。
もちろん、だから、言葉の使い方も安易にしては駄目なのです。
正しい『意見』を述べることが、私たちの生きてゆく上での修業ではないでしょうか。
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school
新人ビジネスリーダーいろは考;第11講:『流転』
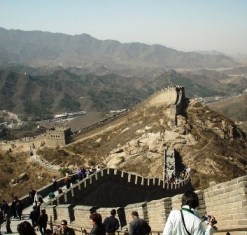
第11話:『流転』
~弘法大師が詠んだ「いろは歌」を使ってビジネス社会で多くの成功体験を積むために~
『流転(るてん)』という言葉はよく仏教の教えの中に出できます。
六道と呼ばれる世界、すなわち地獄、餓鬼(がき)、畜生(ちくしょう)、修羅(しゅら)、人間、天上という状態世界を迷いによって行ったり来たりする。
六つの世界の生死を繰り返すことなんですね。これを輪廻(りんね)ともいいますね。
「輪廻転生」という映画がありました。
また『流転』という言葉を私たち現代人は、宗教には関係ないとして辞書を探してみますと【流】という意味は相続してゆくことなんですね。
【転】という意味は再び起こることなんですね。
「相続」するというのは、だいたい親から子供に財産を引き継ぐときに使いますよね!?
もっと、厳密に考えてみますと遺伝子を引き継ぐ意味と解釈してもいいように思います。
「親の因果が子に報い」などというショッキングな引き継ぎを含んでもいいように思います。
そして【転】で再び起こるということにつながる。
伝わったものが再び起こる。
なんだかちょっとおっかないように感じますね。
でも、ご安心あれ!
これからけったいな宗教にカブレていない方は、私の言うことが本当に正しいということがわかります。
ちょっと偉そうなことを言って恐縮ですが、ぜひ、このあとを読んでください。
皆さんのご先祖様は何人いると思いますか??
だいたい、自分で調べるとしたらお爺ちゃんのお爺ちゃんくらいまでは計算できますね!?
今、自分を0代、父母を一代前の祖先、お爺ちゃん・おばあちゃんを二代前の祖先としますと一代前の祖先は二人ですね。
二代前の祖先は父方の父母2人と母方の2人の4人ですね。
ここで、ちょっと理由はわからなくても結構ですから数学を使わしてください。
0代の私は1人=2の0乗で表します。
一代前の先祖は2人=2の1乗で表します。
二代前の先祖は4人=2の2乗で表します。
ですから、十代前の先祖の数は、
2の10乗で表します。
2の10乗=1,024人になります。
25才でだいたい平均して子どもが生まれ一代世代が更新すると考えましょう。
そうすると一世紀百年で四代さかのぼることになりますね。
紀元前0年までおおよそ二千年ですから80代さかのぼることになります。
80代前のご先祖様の理論的数は2の80乗です!
これは、電卓では計算不可能なほど大きな数え切れない数になります。
それぞれの代の先祖の数をまた累積(総和)してはじめて、私の先祖の総数となります。
もう、気が遠くなるほどの数です!
それでもたった2千年ですよ!
もっともっとさかのぼれば、もう諦めなければならない数になります。
数え切れない数のことを数学では『魔訶不思議』というのです。
少し蛇足になりますが「不思議」という言葉は厳密には「不可思議」なのですね!?
「思ったり、議論できず!」と訳すのです。
そこに「魔訶」とは、「とにかく大きい!」という意味です。
皆さん、絶対にだまされちゃぁダメですよ!
「過去に供養されていない先祖の悪霊がどうのこうの・・・」といって、法外なお金をふんだくって拝んでくれるインチキ宗教者がいるのです!
当たり前じゃないですか!
さきほどの計算からすると先祖の数は、現在の全世界の人口(約60億人)よりも多いのですよ!・・・本当に!
一人や二人、いや千人・万人の悪霊の先祖がいてもいいのですよ。
なんとでも言えるのです!
供養されていない先祖様、野たれ死にした人、また人を殺してしまった人、そして、やっかいな病気にかかった人がご先祖様にはいっぱいいるのですよ。
今、偉そうに裕福に暮している人の先祖にだって、同じ数だけの問題のご先祖様がいたのですよ。
大昔は、戦争して「弱肉強食の世界」で生き抜いてきたのですから。
遺伝子学で研究されているDNAというのには、全部先祖様の「生き様記録」がされているらしいというところまでわかっているそうなのです。
すごいでしょう!?
もう既に刻み込まれた記録を、消すことはチョット無理でしょう。
もちろん、病気に関してそれを消す技術を見つけようと研究者はやっているみたいなのですがね。
だったら、今の自分の記録だけでも子孫に相続しないようにしたらどうでしょう!?
そうすれば、自分のまずいことだけは【転】じることはないでしょう。
もっと自分のこれからを強烈にすばらしいものにして、DNAに刻み込んでみたら子孫へそれが【流転】することができるんじゃないでしょうか。
インチキ宗教者の陰謀にはまらないでください!
過去はさかのぼらず、今を、これからを「正直」に「精一杯」、生きることの方が絶対正しいと思いますよ!
だから宗教心とは、今をまっとうに生きる精神だと思うのです。
毎日を『感謝、感動、寛容』で生きてゆくことではないでしょうか!?
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school
新人ビジネスリーダーいろは考;第10講:『盗む』

第10講:『盗む』
~弘法大師が詠んだ「いろは歌」を使ってビジネス社会で多くの成功体験を積むために~
東京スカイツリー完成間近の頃、上空を飛行しました。(今は飛行禁止エリアになっております!)
『盗む』といったら、聞き捨てならないとおっしゃる方がいるのではないでしょうか?
何もドロボウのことについてお話をしようなどとは思っておりません。
もっと良い意味で、『盗む』という言葉を使ってゆきたいと思います。
たとえば、お手本となる人の「クセを盗む」「技術を盗む」といった言葉だといかがで
しょうか!?
お許しいただけますか?(^o^)
実はもっとすごいことを『盗んで』みたいのです。
それは『生き方を盗む』のです!
私たちは、どうも上手に生きて行くことを教わっていないのではないかなぁと思うのです。
だから、上手に生きている人からその『生き方を盗む』ことにしたいのです。
学校で、このような大事なことを教えてもらった記憶などないでしょう!?
なんだ~、じゃぁ~、『学ぶ』っていう言葉に変えればいいんじゃぁん! と言われるかも知れません。
しかし『学ぶ』については、後日、もっと違った意味でお話してみたいのです。
それよりもやっぱり、『盗んで』みたいのです。
実は私は何を隠そう、過去に本当の『盗み』をしたことがあるのです。
「えっ、なんてふしだらで悪い人なんだよ! こんな人が人生をうんぬんと生意気な!」
とおっしゃるでしょうね。
いやいやゴメン!
初回の執筆にて断ったじゃありませんか! とっくに地獄におちる覚悟で執筆するって・・・。
私は団塊の世代の最後の方にいるのですね。
ちょうど朝鮮動乱が勃発し、日本が特需ブームに乗るころ生まれたのです。
私は、京都生まれで、父親の仕事の関係ですぐに大阪に移り住みました。
最初は、大阪西区立売堀というところだったのですが、幼稚園に入る前、大阪市此花区という場所に移住します。
ここは淀川の河口に近いところでした。
今のユニバーサル・スタジオがある近くです。
私の小さい頃は、まだそこいらじゅう・・・焼野原や戦災を受けたレンガづくりの瓦礫だらけになった建物が
あちこちにありました。そこが男子供たちの遊び場でした。
世間並みに食べ物はあったのですが、まだまだ、充足しきれない時期でした。
私が「盗み」をしたのは、我が家の狭い台所でした。
関西、大阪や京都でのお使い物、頂き物は、ほとんど角砂糖と相場が決まっておりました。
母親の目を盗んで、その角砂糖を箱からつまみ出し口の中にいっぱい入れて、コソコソ逃げ出して行くことを
しましたねぇ~(^^)
学校帰りには、友達と近所のイチジクや柿、スイカをもぎ取って、一目散に逃げ、隠れ家(自分たちで洞穴を
つくりました)に三々五々集まり、衣服がベタベタになるほどガツガツと食べたことがあります。
話せば尽きないほどです。
さて振返ってみますと『盗み』をする時というのは、実に緊張するのですね!
またその実行中というのは、ものすごく集中力(関西ではえげつなくって表現します)が増すのです!
周りの音やかすかな動きにも敏感に反応するのです。
それはそれはいろいろな盗みの方法が瞬時に頭を過るのです。
すごい智恵も出るのです!
私は、このような経験をしておりますから、どうも「技術やテクニック、そして、陳列・レイアウト」などを
先進の企業や先輩から盗む時(といっても、事務所に侵入して図面等を本当に窃盗してくるのではないですよ!)、
すごいパワーが出るのです!
また根っから素直なものですから(自分でこう言うのをお許しください)、すごい発見をするのです。
ビックリするようなことがいっぱいあるのです。
もし、そこの人に何かを教わろうとしているのなら、そこまで集中力が沸くことはないと思います。
限られた時間内で多くの『盗み』をするのですから真剣になります。
その分短い時間で、ものすごい発見ややり方を収穫します。
優秀な職人さんは、みんな先輩の技を『盗む』らしいですね!?
そうしない人は、職人さんの世界には残ることができないらしいですね。
私はかつて、とある料亭の経営のお手伝いをしたことがあります。
県下一の料亭ですから、もちろん板前さんも一流です。みんな一流の人に共通することは目が鋭いこと
ですね。長年に渡って多くのすばらしい技を盗んできたのですから、そうなるのも分りますね。
その鋭さにたまげて・・・後ずさりする人がいます。
一流人は、それをまた見抜くから・・・(^^;
みなさんもご存じのアメリカ初代大統領エイブラハム・リンカーンは、 「人は四十歳になったら、自分の顔に
責任を持ちなさい!」とおっしゃいましたね!?
多くの成功した人達や世の中に貢献した人々をじっくり見ておりますと、ところところで目がキッとなるところ
があります。こんど良くご覧ください。
真剣に人生を生きてゆくためには、いままでやったことのない事、知らない事にいっぱい出くわします。
人から手とり足とりされ教わることは、相手の都合がありますからそう簡単ではありません。
鋭い問題意識と吸収しようとする気持ちは『物事の本質や最高効率の技を心底盗もう!』という気にさせるもの
です。
『盗み心』は神経を周囲に配る習慣を養うものです。
もちろん、刑事事件になるような『盗み』だけは実行しないでくださいね!
今の自分の技術や経験を多くの先輩・先達から『盗む』姿勢が仕事にも良い影響を与えて行きますし、自分の能力
開発に確実に寄与するでしょう。
教えてもらえないのではなく、教わろう、学ぼう、そして『盗もう』とする気持ちがないのです!
カッコだけの生き方より、もっとドロ臭い生き方が本物ではないでしょうか!?
ハスはきれいな花を咲かせますが泥沼で咲くのですね!?
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school
新人ビジネスリーダーいろは考;第9講:『理想』
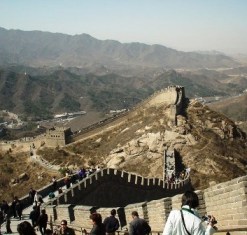
第9講:『理想』
「理想を持つ」「理想を追う」ということばを良く使いますね。
『理想』ってどんなものか考えてみましょうか。
まず、『理想』の「理」の部分ですね。
「理」は「ことわり」と読むのですね!?
意味は百科事典で調べてみれば分るんでしょうけれど、あえて私が感じているままに説明してみます。
「理」には、【発端・原因】がなければならないのです。
そして、その【発端・原因】から色々なことが起こり、【過程】を踏んで【結果】に結びついてゆく一連のことが、きちんと理解され他の人に説明することができるとき「理を知っている」というのです。
だから説明を受ける人が、その「理」が解るとき「理解する」といいますよね!?
「理に長ける」という言葉も、何かの【現象】を突き詰めてゆき、その【原因】を発見する能力を持っていることをいうのです。
さて、次に『理想』の「想」の部分ですね。
「想」という字を良く見てみますと「相手に心を合わして」いますよね!?
もしくは、「心が相手から押し潰されそうになっているのを必死にこらえている」ようにも見えますね?
「想う」というのは、まず、「自分のたった今の心を相手に伝えようとすること!」なのです。
人はいつも何かを考え、感じていますね!?
それを人に伝えることができれば、もしかすると伝わった人から援助・支援を受けたり、手伝ってもらったり、ある人を紹介してもらったりすることができるのではないでしょうか!?
人は何かを想う時、さきほどのように誰かにそのことを伝えることをします。そのとき思いもよらず、周囲の人々から妨害を受け、邪魔されることもあるのです。
「そんなことやったって!」
「何を考えているんでしょう。バっカみたいな!」
などと言われたりするのですね・・・。
この一言で潰れてしまう人が多いようですが、「想」という字をもう一度良く見てみますと、「自分の今の心が押し潰されそうになっても必死でこらえるんだよ!」ということを教えてくれます。
さあ、どうでしょう。
『理想』ということばを、まとめて考えてみましょう。
『理想』とは、心に、「すばらしい自分のあるべき姿」をしっかりとイメージし、そうなるためのこれからの「確実なシナリオ」をつくり、それを「正しく持ち続け」、周囲の人に理解してもらえるように「シッカリと説明し続け」、「多くの人から協力を得る」こと!
そして、そのイメージを実現するために「周囲の雑念に惑わされることなく」、一歩一歩「確実に夢を実現して行く姿」と定義してみてはどうでしょうか!?
『理想』を実現するための手段は、結局のところ「最後までやる!」ためのあらゆる手だてのことであろうと思うのです。
このあらゆることに立ち向かうというか、挫けずにやってゆくための原動力になるのが、「大きな夢と確固たる信念」ということになります。
また、いずれこの『いろは考』で『信念』のお話をしたいのですが、「想」と信念の「念」とをくっつけますと『想念』という言葉になります。
「今の心を想い続ける」ことなのです。
『理想』をしっかり持ち、多くの人に十分理解していただけるまでその理由と実現方法を確立し、『想念』しつづけますと『奇跡』が起こると言われています。
「神や仏に、これからやろうとする正しい想いを祈り続けることによって、神仏の加護が得られる」といったことを多くの成功した人々が体験されております。
かく言う私も実際に、そのような体験をいっぱいしております。
このような体験をしますと本当に自信が身につくようになります。
そして、その自信が次の「夢」『理想』を実現する励みに成って行きます。
とりもなおさず、『理想』は「自分自身の人生観そのもの」になるようです。
自分の人生が何のためにあるのか、自分は何で燃焼しつくすのか、限られたタッタ1回限りの人生、いっぱいやりたいこと、やらねば成らないことを紙に書出してみて下さい。
『理想』は、自分を正しい方向に導いてくれる唯一絶対のものだと思います。
いろいろな宗教のお経や教典よりも本当は大切なものに違いありません。
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school
新人ビジネスリーダーいろは考;第8講:『知識と知恵』

第8講:『知識と知恵』
「知識」と「智恵」とは違うのですね!?
私の行っている新入社員研修・訓練を経験した人ならご理解されます。
「社会人への洗礼」なんて言って、かなりショッキングな教育・訓練をします。
「知る」「わかる」と「出来る」「出来た」はまったく違うのですね。
学校では99パーセント「知る」「わかる」で点数がつけられ順位がついてきたのです。
記憶力や計算力を基準に「良い子」「悪い子」がだいたい決定されてくるのですから、・
・・これは危険ですね!?
人間の能力はおおよそ140個ほどに分けることができるそうです。
しかし計測・測定できる可能な能力はたったの70個ほどだそうです。
「人の心を読んだり、先のことが予知できたり、スマイルを継続できるこころもち」など
は到底測ることなどできませんよね。
「知識」というのはほとんど記憶力なんですね。
「知る」「わかる」の部分なんですね?ですから、多くの本を読んだり、人の話を聴いた
り、テレビや映画を観ることなどでどんどん知識は増えてきます。
この世の中は何事においても差がつく、差がつけられるのだということは当たり前なので
すね!?
ここに「カラス」と「カモメ」を連れてきます。
ほとんどの人は無意識に「カモメ」はかわいいとか「好きだ」とかいいます。
「カラス」には申し訳ないのですが、大多数の人が「嫌やだ」と発言します。
なぜと言われて、理屈で説明できる人はそんなにいないのです。
でも、マスコミに時たま取り上げられるカラスで「利巧なカラス」がいますよね?
そのカラスは、ほほ笑ましい動作をしたりするからなのです!
最近の動物園ではいろいろな動物が調教されて物見にされていますが・・・、さすがに
カラスが飼育されたり、調教されたりはないです(^^;
なにが言いたいかって?
どんな見栄え・外見でも「好まれる特徴」を持つ知恵があると、いいのだということなの
です。
し話がそれます。
人は「感じる」から動くのです!
辞書に「理動」と言う言葉がないのは「人は理屈では動かないんだ!」という証拠なのです。
どんなに理由や理屈をつけても、結局は納得と感じたからこそ気持ちよく一所懸命に人は
頑張るのです!
とにかく人は無意識に「奇麗な人」とか「感じのいい人」とかを感じるのです。
それは別名「差別」なのです。
「差別・差別」と叫んでいる人だって、食べるもの着るものを選んでいるはずです。
それだって「差別」をしていることなのです。
すなわち、人は皆んな比較する対象があると優劣をつけるのです!
とりもなおさず差をつけているのです!
だから、世の中に競争が発生します。
この競争によって、今までの発明や発見を人間にさせてきたのです。
品物の品質が良くなったり、サービスが良くなったり、おいしくなったり、使い勝手が
良くなったりするのはみんな競争のおかげだといっても過言ではないと思います。
「発明」や「発見」、「勇気」や「努力」はすべて『智恵』が発揮できたからなのです。
そして、これらの後押しをしているのは「人さまに喜んでいただこうとする心」のように
思います。
人から賞賛されたいという心も「正常な智恵」なのです!
全部、「智恵の源泉」なのです。
この必要な「智恵の出方」は、多くの過去からの先人・先達が発見・発明した原理・原則、
定石、経験則などの「知識」の量によって差がでてくるのですね!?
やっぱり「智恵のある人」は「多くの知識」を体系的に持っているようなのです!
でもご安心あれ!
この「多くの知識」のこれまたほとんどは社会人になってから持ち合せるのです。
人は、多くの難題にぶつかったとき、その時その時に「智恵」が必要となってきます。
そんな場面に出くわすと「問題意識」が芽生えます。
この「問題意識」が、積極的に多くの「知識」を得ようとするようになります。
そして「意識の深まり」と「知識の蓄積量」がある点に達しますと(これを専門的に臨界
点、もしくは閾値と呼ぶそうです)周りの人々もビックリするくらいのことをしはじめた
り、新しいやりかたを発見したりするようになります。
もちろんヘコタレたりもしなくなります。
最後までやる勇気も備ります。
もっとすごいことは、自分の「知らない」、「できない」ことを素直に認めることができ
るようになります。
だから、「知らない」ことや「できない」ことを周囲の人の力に頼るようになれるのです。
また自分の手に追えないことがらについて「知る人」「できる人」を探しはじめるのです。
いままで以上に真剣に探しはじめるのです。
ついに、その人に出くわすんです。その人を師と仰ぐことができるのです。
吉川英治さんが「人皆我が師」とおっしゃっているとおりになるのです。
不思議なことに、その師は「我が子」であったり「自分の後輩・部下」であったりする
ことが多いようなのです。
もっとあります!
今まで見慣れてきた風景が、ものすごく奇麗に美しく見えてくるのです!
自然界がこんなにもスゴイものかと本当にびっくりするのです!
幸せいっぱいでいつも笑顔でおられるようになるのです!
「智恵のある人」は顔に顕れるようです。
言葉にも顕れます。
行動にもあらわれます。
「智恵のある人」はまるで何でも知っているような、何でもできるようなガッシリとした
重みと包容力を感じさせます。
セコセコしていません!
そばにいるだけで安心ですね。
少しでもいいから、そんな人に近付きたいですね!
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school