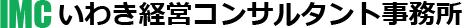ブログ
新人ビジネス・リーダーいろは考;第28講:『苦言を呈する』

第28講:『苦言を呈する』
『苦言を呈する』というのは、警告、忠告をすることです。
皆さんはどれくらい素直に、『苦言』を受けることのできる人を周りに持っていますか?
人間と言うのはとかく、ちょっと成功をしますと調子に乗ったりします。
私は多くの人から「先生、先生」と呼ばれます。
本音を言いますとチョット恥ずかしいのです。
しかし自分の名前と同じで何度も「先生」と言われているうちに、「先生!」と呼ばれますと条件反射的に返事をしたりします。
ですから、自分に対していつも「先生・先生と呼ばれるほどバカじゃない!」と言い聞かせます。
何も先生と呼んでくれた人に対しての反発を持っている訳ではありません。自分自身に「調子に乗るなよ!」と言い聞かせているだけです。
私の周りにも、たとえば国家資格に合格したり、非常に短期的に成績が上がると「態度が偉そうになる人」がいます。
たぶん本人は気づいていないのですが・・・。
そのようなタイプの人に限って他人から「良くやった」と誉められたいのですね!?
また「褒め言葉」を何度も言って欲しい人がいるのも事実です。
でも、他人はそんなに何度も誉めてはくれません。
それよりも、その人にとってもっと上のステージを狙わせるためにより大きな課題を与えることがあります。
このようなとき、相手の心からの励ましなのに「あの人は誉めてくれない!」と勘違いする人がいるのですね。
その心は態度になって顕れます。
たとえば健康上の問題を提起して、
「自分は健康を害するくらい働いているのに!」
とか言ったりします。
また巧妙なサボータージュ(サボり)をする人もいます。
親戚の人が全部死んでしまうくらいの悔やみや法事をつくり休んだりする人もいるのです。また結婚式など、むやみやたらとオヨバレした理由で休みを取ったりします。
有給休暇は、さも当然と取ります。
こうなりますとなかなか、その人とコミュニケーションを交わすことなどできませんね。
上司や先輩からすると『苦言を呈する』こともできなくなります。
先ほども言いましたように『苦言』というのは忠告や警告なのです。
「こんなことしているとこうなるよ!」とか、「これからこうするともっと良くなるよ!」
というのが『苦言』なのです。
『良薬、口に苦し!』という格言がありますが、まさに『苦言』はそれなのです。
しかしプライドが高かったり、有頂天になっていたりしている人は『苦言』が耳障りなんですねぇ~。
こういう状態では、もちろん素直になれませんね!?
素直というのは「心を開ける」ことから始まります。
また後日のブログで述べますが、『中心観』という非常に重要な判断基準がないと真実が見えません。
『中心観』は「何が正しいか」の基準なのです。
この「何が正しいか」を理解するためには、正しい経験を多く積んだ上司や先輩から教わらなくてはなりません。
あやや・・・どうも「ニワトリが先か卵が先か」になってしまいました。
さて『苦言』を素直に聞けるようになるためには、いつもどうしたらいいのでしょうかね?
それは上司や先輩のいいところをいつも見るようにすることなのです。
特に仕事において、自分よりもはるかに優れているところを多く見つけて認めようとすることです。
もちろん、その人にも欠点や短所があります。
どんな人も聖人君子じゃないのですから間違いや欠点はありますよ!
それを聴きたくない理由にしていたのでは、誰からも学べませんね!?
最もいい方法は、自分から『苦言を呈して』もらう姿勢を見せることでしょうね。
大変に難しいことですが、自分を積極的に成長させるためには非常に重要なことです!?
世の中で成功している人には必ずといっていいくらい、『苦言を呈してくれる師』がいるようです。
逆境にあるときよりも順境にあるとき、あえて自分から進んで『苦言』を承りに師のところに行く人すらあります。
私の仕事は経営のお手伝いなのですが、もちろん、委託される企業トップ、CEOや代表取締役社長と接することが圧倒的に多くなります。
経験上、立派な経営をしている、利益を上げている社長ほど
「先生、どこか間違っていたりしませんかね?」
と質問されます。
私はですから、間違っていたり、勘違いしていると感じたことはハッキリ言わせていただくことにしております。
ダメな経営をしている社長は、残念ならが褒め言葉が欲しいくせに社員の悪口が多い(^^;
私は『苦言を呈する』ことこそミッションだと確信し、厳しいことを申し上げますが、必ず、素晴らしい社長ほど感謝の言葉を返えしてきます。
そして、また、一歩一歩経営を着実に良くされています。
逆に『苦言』を受けることがとにかくイヤな人は、どうしても素直になれない分、成長が遅いものですから、他の人との変なライバル心が出来てしまうのですね。
最悪の場合は、はるかに後輩である人に対しても、上手く行かない苛立ちからライバル心が先行してしまい、自分が指導や導く立場にありながら、敵対心でつき合うことになってしまい味方がドンドン少なくなって、仕舞いには孤立しますね(^^;
「あの人は仕事はできるが、人ができていない!」となってしまいます。
ですから、ちょっと差別的な言い方をするようですが、「職人」になってしまうのですねぇ~。
経営では「赤字」になったことを正当化する『アホ・バカ社長』がいます。
「赤字」は正しくない経営の姿なのですから「素直に指導」を受けるべきなのです。
しかし根がアホ・バカだから、やっぱりそれができない(^^;
ダメですねぇ~。
『苦言』=『良い薬』をぜひ都度々々飲みましょう(^^)
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school
新人ビジネス・リーダーいろは考;第27講:『教える』

第27講:『教える』
『教える』ということについてお話しします。
その前に、作者不祥なんですがすばらしい言葉がありますので紹介します。
『教える』『教わる』ものの心構え
一.教える(愛しむともいう)とは、為すべきように覚して知らす導をなす。
一.教えの根源は、愛である。故に教えるものは、常に、あきず、焦らず、腹立てず。
一.教わるものは、逃げず、ひっこまず、言い訳をせず。
以上を絶対に支柱にしなければ教えの実りはない。
『育つ』は、『巣立つ』が元言葉。
『巣立つ』まで手塩にかけることをいうのである。
『手塩』とは、おむすびをつくるときの母の心である。
いかかですか?
『教える』というのは為(な)すべきように、すなわち、「どうやるのか」をしっかりと覚えさせるのですよ!
そのための「知識」「原理原則」「定石」を教えるのですよ! といっています。
『教える人』は、「知る」・「わかる」・「できる」までの指針をしっかり持っておかなければなりません。
長年の経験によって「できる」域にきていても、その理由、理屈を知っていなければ、人を『教える』ことはできません。
ただ「できる」というのであれば、チェーン・ストア業界では、「職人」すなわち「ワーカー」としか見ません。
私は人事制度の中に必ず、内部資格試験や外部資格試験を登用基準に入れることを推奨します。
それは本当のプロであれば、知っていてあたりまえの知識を体系的に理解しておくことが必要だと思うからです。
また学問だけの知識や理論に対してキチンとした反論、批判ができるのもプロだと思うのです。
ですから、たとえば、スーパーマーケットでは「販売士」や「調理師」の資格は取れてあたりまえと考えるのです。
なんだかんだと「資格と実績とは違うんだ」と言ったり、「資格など取らなくったって商売はできる」と言う人がいます。
これは「屁理屈の言い訳」でしかありません。
社長はもちろん、資格など持たなくてもいいのです。
社長は、自分よりも優秀な人財をどれだけ多く得るか、創るかが仕事だからです。
(経営とは、凡人を非凡にすること)
しかし、店長、支店長、バイヤー、スーパーバイザーやインストラクターになる人は、「販売士」や「調理師」などは取っていて当たり前です。
情報システムを構築する人は「情報処理技術者」の資格を取っていてあたりまえです。
難度は別です!
チェーン・ストアを構築してゆくには「職人」はいりません!
大変に生意気な、差別的な言葉を使いますが非常に大切なことなのです。とにもかくにも「勉強する社風」が必要です。
『教える』ということは、大変なエネルギーが必要です。
先ほどの言葉にも「愛が必要、あきず、焦らず、腹立てず」と言っています。
我慢・忍耐が『教える人』には必要なんです。そのために苦労を知っている人でなければならないのです。
『苦労は買ってでもやれ!』というのも至言なんですね。
また、もう一つ、こんな言葉も紹介しましょう。
『学んで足らざるを知り、教えて致らざるを知る』
多くの知識に出会い、多くの成功者から学びますと「本当に何も知っていないなぁ!」ということが分ります。
そうしますと止ることを知らないくらい貪欲に仕事などに関する本をいっぱい読むようになります。
人に『教えて』みますと「本当に理解していないなぁ!」と恥じ入ることがいっぱいあります。
ですから、真実を見ようとするようになります。
私は、この真実を見ようとする姿勢のことを『中心観』といっています。
『中心観』ができますとブレないですね。
『教える』側に立ったときに、「何が正しくて何が間違いかで教えること」と「好き嫌いで教えること」との違いが分るようになります。
意外と公平に公正に『教える』ことができるようになります。
『教える』ことの精神は『手塩』であると最初のことばにあります。
機械でにぎったおにぎりと、手でにぎったおにぎりは絶対に味が違います。
もちろん手でにぎった方が断然にうまいですね!?
他人まかせの『教え』はないよ! という意味です。
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school
新人ビジネス・リーダーいろは考;第26講:『能力』

第26講:『能力』
『能力』について、いよいよお話する時期になりました。
『能力』をひとつひとつ分解してゆきますと約140個ほどあるらしいのです。
その中の半分の約70個ほどは測定が可能らしいのです。
たとえば、走る能力となると100メートルを何秒で走ったかとか、1時間に何キロメートル走れるかとかストップウォッチがあれば測れます。
実は、今まで学校で優劣をつけられてきましたが、学校ではすべて測定可能な能力だけを測るのですね。
ですから、学科は全部百点法とか、5・4・3・2・1とか、秀・優・良・可・不可とかで定量化されます。
これでもって、優劣、序列をつけるわけです。
ちょっと、変だと思わないでしょうか!?
残りの70個ほどの能力は、どのように判断されるのでしょうね?
まず通信簿なら、先生の感覚、感情で、寸評のような形で表現されるだけです。
もしくは、まったく評価されません。
さて、あなたの数学の成績が5だったとしましょう。
もしくは、英語が5だったとしましょう。
今働いている会社や職場で高度な数学を使う部署があるでしょうか?
毎日、英語を使う部署があるでしょうか?
もちろん将来、海外買い付けが始まったりすれば、英語を読んだり、書いたり、話したりできる人が必要になります。
でも今、これらの能力が長けているといっても、今働いている会社や職場で仕事をしてゆく上では、宝の持ちぐされでしかありません。
測定できない能力には、たとえば「人の心、気持ちが読める」とか、「商品の相場が天候とかいろいろな条件のもとで変化してゆくのを適格に予測できる」とか、「誰とでも仲良くできる」とか、「接客が上手」とかがあります。
いかがでしょう!?
測定できない能力の方が、生きてゆく上で、仕事を効率よく進めてゆく上では大事だとお思いになりませんか。
「あの人がそばにいると周りが明るくなる」
「なんとなく、あの人のそばにいると安心だ!」
「あの人がくれば実績が上がる!」
「あの人だったら、人を説得できる!」
「あの人は果物のことだったら生き字引のようだ!なんでも知っている!」
「あの人の閃きはものすごい!」
「どうも、お客様はあの人に会いにきている!」
という具合に測定できない何かを持っている人の方が、実社会では能力のあるように思いませんか。
そのとおり!
実社会における人付き合いや仕事のこなしかたが最も大切な能力なのですね。
そんな能力を持っている人とを「実力のある人」といいます。
『能力のある人には地位を、実績の上げている人には録を』
という言葉をご存知ですか?
多くの企業の人事賃金制度の基本理念なのですね。
『能力のある人には地位を』という意味は、仕事をこなすための知識、経験、そして、仕事に取り組む精神的態度が高い人には地位(職位:主任、店長、所長、課長、部長、役員などの肩書き)を与えようということです。
それはとりもなおさず、能力のある人にはいい仕事のできるチャンスを与えようということに他なりません。
チャンスを活かすも殺すも、それは本人次第なのです。
やっぱり能力のある人は、だいたい実績を上げますね。
ですから『実績の上げている人には録を』が活きてくるのです。
もちろん地位を与えられていなくても真面目でコツコツとチームの実績を上げるための縁の下の力持になっている人も録で処遇されるべきです。
それじゃ・・・、『会社においての能力』は、どのように評価されるのでしょうね。
今働いている会社や職場では、「パワーアップ評価」「資格制度」がそれに当たります。
社内の本当に必要とする資格を取れば、『能力』がまず認められるのですね。
だから、チャンスを与えてもらえる通行手形をもらったということになります。
ところが、この大切な制度に対して消極的であったり、なんだかんだとヘ理屈を言って、それに参加しようとしなかったり逃げる人がいます。
残念なことですが、このような人はやっぱり、どこの世界にいっても同じでチャンスに出会えません・・・。
人生は、
「チャンスに出会う回数」 × 「チャンスを発見できるタイミング」
× 「チャンスをものにする実行度」
なのですね!?
チャンスに出会う回数が、ゼロだったら全部ゼロになってしまいます。
自分自身で測定の難しい「人の気持ちのわかる」「今、何が大切か」などの『能力』を磨く努力をしたいですね。
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school