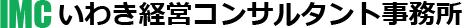ブログ
飛行機の世界から学ぶ経営いろは考:第14講;『傾向Tendencyその1』:P-Factor(プロペラ・ファクター)

第14講;『傾向Tendencyその1』:P-Factor(プロペラ・ファクター)
先週は、とある企業の経営診断報告書の作成で悪戦苦闘しておりました。
病院の健康診断と診断書は簡単ですよね!?
コンサルタントにとっての経営診断とその後に必要不可欠な経営診断報告・勧告・指導書作成というのは大変なのです(^^;
ハッキリ言って・・・割に合わない(^^;
そんな愚痴をこぼしながら、パイロット・コンサルの経営いろは考に着手(^^;
離陸中や上昇中に飛行機が勝手に左へ旋回をしようとする傾向のことを「Left Turning Tendency」と言います。
私たちの生活場面やビジネス場面でも『傾向』ってあるでしょう?
こちらは飛行機の航空力学でのお話になりますので・・・余りにも難しいと感じたら、飛ばし読みか? 最後の方までトラップ(飛ぶ)されてもOKです(^^)
左へ旋回をしようとする傾向(Left Turning Tendency)には、4つの理由があります。
これらの4つの理由はすべて、回転するプロペラによって発生します。
エンジン高出力の時(プロペラが最高回転状態に近い)に強く発生します。
特に飛行機が低速状態では翼の勢いが少ないので、余計顕著に影響が出ます。
ですから・・・、飛行機というのは低速状態が危険なのです。
実は、離陸というのは飛行機が低速状態から浮き上がる状態です。
また巡航飛行から、上昇しようとしますと飛行機の揚力を作るため機首を上げます。
その時、飛行機はスピードが落ちてきます。力学的には、スピードのエネルギーが揚力に変換されます。
どちらも・・・、エンジンは全開状態です。
まず「プロペラ・ファクター(P-Factor)」と呼ばれる力が発生します。
本当は実物を写真でお見せしながら説明しなければ上手くご理解できないかも知れません(^^;
その理屈を米国の飛行機専門分野のYou-tubeで動画説明されています。もちろん英語ですが、理屈が判るのでご覧下さい!
1) https://www.youtube.com/watch?v=TYn1GrvtPXU
2) https://www.youtube.com/watch?v=Zf7-nSMLnMo
飛行機の機首が通常の水平状態よりも上向きになった場合、プロペラに当たる風の向きが変わります。
そのため、左右のプロペラに出来る相対風(Relative Wind)の向きがちょっと変わります。
角度の差は小さいのですが高速で回転しているため、その作用が大きく出ます。
右側の下がるプロペラ(Ascending Propeller)には風が下から来る様になるので、推力が増えます。しかし、左側のプロペラは上の方から風が来る様になるので、まぁ~上から押されると想像していただくと推力が減ります。
右側が強く、左側が弱くなるので機首が左に曲がろうとします。
これを「P-Factor」と言います。
この「P-Factor」が生まれると、右側のプロペラがより多くの推力(前に進もうとする)を発生させますので飛行機は左に行こうとします。
エンジンの出力が高い(高出力)時は、全体の推力発生も大きくなります。
自動車ではこんなことは起こりません。ですから、アクセルと同様の飛行機のエンジン・パワーの操作だけで飛行機はどこかに動こうとするのです。
特に機首の上向く角度が大きい時ほど、この現象が大きくなります。
飛行機の専門用語では、Pitchが高くなると強くなるといいます。
そしてまた機首が高いと(上向く角度)、自然と飛行機自体が低速にもなるので、翼や操縦桿、尾翼の作用も小さくなって「P-Factor」がより大きく感じられます。
ここからは、飛行機の勉強をされている方々向けの書き方になりますが、
「High Angle of Attack」=「機首が高い」=「左右の差が大きくなる」=「 P-Factorが強い」
別の書き方をしますと、
「High Pitch」 + 「Slow Airspeed」 +「 High Power」 で「P-Factor」が強くなる。
飛行機は離陸上昇中に機首を上げすぎますと・・・左に強く曲げられ、放っておくと左旋回しながら傾きはじめ、失速することがあります。
飛行機を操縦しますと、この「P-Factor」は簡単に感じます。
ちょっと機首を上に上げてやると直ぐに感じます。飛行機は直ぐに左に行こうとします。
そのため、機首上げをした時は右のペダルを踏むという訓練をします。
実は、余裕ができてきますと上昇のために機首上げしますとこの「P-Factor」の作用によって計器(Turn Coordinator:旋回釣合計、旋回傾斜計)にあるボールが右側に流れのを見ることができます。
それを修正するために、米国の教官は優しく”Right Rudder"と言ってくれます。
日本のクソッタレ教官は、偉そうに「ホラッ!右ラダーだよ!」と怒鳴ります。
また米国の教官は、
「操縦のコツですね・・・前をよく見て、機首の上げ下げが有っても飛行機の向きが変わらない様にすることなんです。一番良い方法はは、落ち着いて風景を見ながら、風景が左右に移動しなければ計器を見なくてもボールは真っ直ぐとなってます。前を見ても分らない時は、貴方のお尻に掛かる力が左右同じであればピッタリなんですよ(^^)」
と優しいのです。
日本のクソッタレ教官だと、
「ホラァッ! 曲がってっだろう! 水平線が動いてんだろう! ケツで感じろ!」
でも・・・、晴天下の上昇中には水平線・地平線って見えません(^^;
米国の教官でしたら、もう一つのコツどころを教えてくれます。
フロントガラスの向こうではなく、左右の窓から見える水平線、地平線と飛行機の主翼との位置関係で風景が左に動いていないか判る方法をを教えてくれます。
だんだん計器を見るより、風景を見る癖を付ける方がはるか早く、「P-Factor」や他の「Left Turning Tendecy」に対応できるようになります。
さて今回のビジネス・リーダーへの、飛行機の理論からの教訓です!
飛行機は上昇中に左に回ろうとする傾向があるのです。
4つあるその一つが「P-Factor」なのです。
企業・組織の上昇中というのは、成長・発展中、売上げ上昇中のことですね!?
企業は特に、売上高が上がってきますと何が発生するかといいますと、多くの組織でのやるべき事の量(作業量)が増えます。
今までの人員で、その作業量をこなそうとしますから、間違いなく負荷が掛かるわけです。
そのことを知らないでぬか喜びするビジネス・リーダーも意外と多いのです!
どうなるか・・・?
作業を担当する人たちは、自身の作業に意識集中、手一杯状態となります。
上昇氣分になる人と(右プロペラ)と下降氣分になる人(左プロペラ)が必ずいます!
そうしますと・・・コミュニケーションを取ることがおろそかになるのです。
本来なら、まっすぐに全社員の意識ベクトルが向かわなければならないのに、どこかで、誰かのベクトルがズレるのです。
「忙しい」=「心をなくす」と・・・、全体のベクトルが変な方向に向かうのです。
それを直ちに感じ、修正をする役目を担っているのがビジネス・リーダーなのです。
国家は国民主権なとど難しいことを言いますが、経営はビジネス・リーダー主権であるべきです!
これは飛行機でいいますと乗客主権ではなく、全責任を負うパイロットが全権限を持つことと同じことなのです!
実は、パイロットでも機長のことをPIC(PILOT IN COMMAND:ピーアイシー)と呼びます。
そうなのです!
ビジネス・リーダーは、コマンドを矢継ぎ早に発する人でなければなりません。
自分自身が、作業に没頭して汗水垂らすことが立派なことではないのです!
冷静に状況を把握しながら、都度々、やり方の変更、新しいやり方の追加をするのです。
これを「命令の変更・追加」と組織論では言います。
言い方は、敬語を使っても、クソッタレ教官のように言ってもいいのです。
とにかく、部下はあなた・・・ビジネス・リーダーのコマンドを待っているのです。
「氣を使うな! 金使え!」って、良く皆さんに言いますよね!
企業・組織は、従業員に気を遣う慈善事業をやっているのではありません!
営利の優先をして、それを実践し、社会のお役に立って、従業員の・組織員の幸せを追求するのです。
社員・従業員・組織員のご機嫌を取って、言いなりになり、あらぬ方向に組織が向かうなんて邪道なのです!
しっかりとラダーを踏んで(舵取り)をしましょう(^^)
次回は『傾向Tendencyその2』:Torque(トルク効果)から学んでみます。
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school