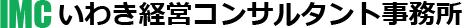ブログ
飛行機の世界から学ぶ経営いろは考:第30講;『高度計規正(Altimeter Setting)』

第30講;『高度計規正(Altimeter Setting)』
最近では精度の高いGPSを使って、正確な高度を知る計器を設置している飛行機もありますが、普通の飛行機で使われている高度計(Altimeter)は気圧を測定して、それを高度に換算しています。
ですから、飛行機から長い長い重しの付けた巻き尺を地面に落として高度を測るわけにもいきませんね!?
実は、カシオで出している本格アウトドアギア時計:PRO-TREK・・・・(決して回し者ではありません!)も高度は気圧によって測定しております。
残念ながら、実際の高度を測っている訳ではないのです。
気圧は、場所・時間によって時々刻々変化しますから、どうしても修正が必要になります。
それを「高度計規正(Altimeter Setting)」と言っております。
気圧を計って高度を表記するのが高度計(Altimeter)なのですが、意外に正確なのです!
気温変動などで誤差が出ますが、すべての飛行機も同様に気圧を測定し高度を計算していますから誤差も同じなのです(^o^)/
ですから「高度計規正(Altimeter Setting)」をすべてのパイロットがきちんと行えば、高度計誤差による航空機同士の空中衝突は基本的に起こらないと考えていいのです!
多くのパイロットは離陸前から飛行中、着陸直前に、ATC(Air Traffic Control;航空無線)を聞きながら「高度計規正(Altimeter Setting)」を行います。
FAA航空法では100マイル(約160km)以内の数値(日本の航空法は160kmとなっているのはFAA米国に従属しているからです!)で大丈夫だとされています。
高度計(Altimeter)は地面標高(Field Elevation)を表示しますが、気温や気圧の変化で地面からの本当の高さには多少の誤差があります。
離陸前に、「高度計規正(Altimeter Setting)」を行い、地面標高(Field Elevation)を高度計(Altimeter)に表示させます。
普通に飛行する場合、最低でも地上から1,000 feet(約300m)、山間部で2,000 feet(約600m)の余裕を持って飛行します。
ですから飛行機同士の衝突の可能は、パイロットの操縦ミスが圧倒的に多いのです!
高度計(Altimeter)の中央右側に小さな窓があります。その窓には、現在の気圧を表す表示があります。高度計の左下にツマミ(ダイヤル)があります。
それを回しますと、小さな窓の気圧数値と高度計の針が動くようになっています。
離陸前に入手した気圧、飛行中に傍受した気圧を高度計(Altimeter)の小さな窓にある表示気圧と合わせますと、高度計の針が動き、観測地点で正しくその場所の地面標高(Field Elevation)を表示します。
概算として、表示窓の数値を0.1変えますと約100feetの表示変化があります。
実際はもう少し微妙なのですが、十分正確な目安数値です!
この「高度計規正(Altimeter Setting)」は、基本的に空の上を飛ぶ総ての飛行機が、同じ高さの値を共有するためにおこないます。
同じ飛行場で、ほぼ同時刻に離陸した飛行機がたとえば、気圧の低い所に向かいます。
「高度計規正(Altimeter Setting)」を修正せず気圧の低い場所に行き飛行を続けますと実際の高度が表示より低くなってしますのです。
そこに障害物などがありますと衝突の可能性が出ます。気圧の低い所に向う時は注意が必要なのです!
気圧の表記の仕方に何種類かありますが、ここでは1個だけ例示します。
QNHという単位を使います。
QNHというのは英語では、Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the groundと言い、海抜高度10feet(でも高度ゼロと呼びます)を得るための高度規正値のことです。
飛行場がある標高での気圧高度計の表示が正しい海抜標高を指すよう規正されているとき、高度ゼロに対応する気圧として計算されます。
その他にもQNE, QFEなどという単位が使われますが、試験を受けない人には必要ありませんので割愛しますが、この表記は・・・なんの頭文字なんだろうと・・・飛行訓練初期の段階で悩みました。
例のクソッタレ教官に聞いても「そんなもん、調べりゃわかるだろう!」の一喝(^^;
同じクラブ仲間に聞いても、分からないと言うのです。
実は、QNH、QNE、QFEとうのは、どれもモールス符号が使われていた時のQコード(またはQ符号)なのでした(^^;
何か英語の頭文字ではなく、説明が本節から逸れますので以下のURLでお調べ下さい!
https://ja.wikipedia.org/wiki/Q%E7%AC%A6%E5%8F%B7
「高度計規正(Altimeter Setting)」のことを通称「QNHセッティング」とも呼びます。
ある空港の管制塔から送られた海面気圧値を、高度計の気圧セット・ノブを回して、その気圧値に合わせますと、高度計の指示はそこでの海面上からの高度を指示するのですね。
これですべての同じ空港を離発着する飛行機の高度計は同じ値を示すこととなり、安全性が格段に向上します!
日本(洋上を除く)では、平均海面上14,000ft以下の高度飛行する飛行機は、QNHに高度を規正しなくてはならないことが航空法で規定されています。米国では、18,000ftです。
実はここに来てやっと、飛行機での操縦で注意しなければならないことを知ったかぶりします。
高度計を調整しなければ、地域の気圧差で飛行高度が変わってきます。
パイロットはその都度、気圧変化に対応する為、飛行中には近くの気象情報を発信して折る管制塔などからAltimeter Settingの情報を得て、「高度計規正(Altimeter Setting)」をしなければなりません、
気圧の低い所から高い所に飛行するのには大きな問題はありませんが、低気圧に向って飛行する時は注意が必要なのです!
特に低空や大きな障害物がある所、山岳地帯では非常に注意しなければなりません。
パイロットは自身では十分な高度を取っているつもりでも、気圧が下がって行きますと高度を保とうとして同じ気圧の層(Pressure Level)を飛行しようとします。
最悪の場合は気圧変化に気づかず、障害物や山に衝突してしまします。
気圧の低い所に向って飛ぶ時に、「高度計規正(Altimeter Setting)」をしなければ、実際の高度がドンドンと下がって行きます。
障害物がよく見いえていれば、回避行動も出来ますが、障害物が見えなかったりすると衝突してしまいます。
有視界飛行(VFR)で飛行している私のレベルではまだマシなのですが、計器飛行で雲の中を飛行する場合は非常に危険です!
このまま書きますとまだまだ長くなりそうです!
もう飽きてこられたかも・・・?(^^;
続きは次回にします。
さてこれからが本番、ビジネス・リーダーへの教訓です。
企業・組織において、経営計画・事業計画を策定されていますよね!?
もちろん、行き当たりばったり企業・組織も星の数ほどお見受けしますが・・・(^^;)
もしくは、月次での販売計画、行為目標を設定し、それに邁進する企業・組織はまぁ~普通ですね!?
ここで定義をします!
【マネジメント】とは、数値と状態との目標を、期限までに達成することを いいます。
【コントロール】とは、命令の追加・変更と、教育訓練の追加をいいます。
ちょっと話は逸れますが、【マネジメント】の定義をより深く考えて行けば、おのずとマネジメントのできる技術を持つ人を「マネジャー」と呼ぶのだというのが分かりますね!?そうなのです!
企業・組織において、数値と状態との目標を、期限までに達成することが幹部・管理者に与えられた任務(責務)なのです!
任務(責務)を果たし続けることのできる者が「マネジャー」なのです!
ここで「藤本のマ・ミ・ム・メ・モ理論」というのを紹介します。
マ:マネジャーのことです。
しかしマネジャーに成れない人は、「ミ・ム・メ・モ」を頭文字にする精神構造があります。
ミ:ミテネンジャァー;
観てないのです! 現場・現物・当事者を! 頭でっかち、格好ばかりの見せかけ管理職もどきに多いのです! 肩書きだけは一人前ですが、椅子から立ち上がらなくて、レポートの量は多いが、中味が薄く、実績が伴わない!
ム:ムリシテンジャー;
無理するのですねぇ~(^^; 特に新任管理者は・・・(^^;
そのために力んだムダな力がどこかに飛んで行き、実力発揮できない(^^;
メ:メゲテンジャー;
そうなってくると・・・メゲるのです(^^;
ヘトヘトになって、効果・実績が上がらなくなり、どうでも良い気分の直前状態にまで陥ります(^^;
そして最後に、
モ:モう・・エエンジャーとなるのです(^^;
それで・・・続きとなります。
「マネジメント」を行う上で最も重要なことが、途中経過チェックですね!?
「マネジメントのPDCS(F)サイクル」は、Plan(計画ありき)から
始まります。計画に基づいて実践・行動をして行きますから、徐々に成果が上がって当たり前です!
最後の最後に蓋を開けて「なんじゃぁ~コレ!?(^^;」ではいけません(^^;
やはり、途中途中できちっとしたチェックポイントを決め、そこでの経過推定目標と実際のギャップを知るべきです!
ここに「高度計規正(Altimeter Setting)」と同様の補正措置が講じられなければなりません!
もし状況が推定・仮説した状態とはならず下方にギャップが存在することがあります。
この原因をシッカリ探り、その対策を打たねばなりません!
原因の真因は簡単です!
「やり方が間違って」のです!
だったら・・・どうするか?
「やり方を変える」のです。すぐさま、組織要員、もしくは当事者に対して、やり方の変更を「命じる=命令」すべきなのです。・・・「命令の変更」もちろん、言葉づかいは命令調でも、お願い調でも何でも良いのです。
組織論から言えば、上司・上長が発せられるものはすべて「命令」なのです。
ですから、部下は「命令に服従」が当たり前です!
「命令の変更」に際して、部下が参画してその変更方法を一緒に考えるのはより良しです!
「命令」を変更したらどうなるのでしょう!?
まずは、まったくやったことのないことをしなければならない「命令」であったり、「やり方」がまだ未熟な者もいます。
だから、「教育・訓練の追加」が必要となるのです!
以前にも書きましたが、
教育とは、考え方をプラスにすること、思想・方針を教え込むことです。
訓練とは、できる腕前づくりです!
「マネジメント」と「コントロール」が逐次、一対となって事がなされてゆくのです!
そこに常に状況を把握しながら、「調整」「規正」が必要となります。
そのための手立ては、これまたすべてに言えるのですが「基準」「規定」「規則」という正しい「物差し=尺度」が必要なのです。
この「基準」が企業・組織にどれくらい明確に揃っているか?
「命令の変更」が、躊躇なく「朝令暮改」でできるか?
「命令」が出されたなら即刻、適時に「教育・訓練」がなされるか?
この一連のプロセスがきちんとできる企業・組織の文化レベルは「高い!」というのです。
しかし残念ながら、コト起こって右往左往し、誰もなにもしない(^^;・・・、そして、誰も責任を取ろうとしない・・・、最悪は、結果は「社会のせい」「世間のせい」「政治のせい」「行政のせい」「他社のせい」「他人のせい」・・・最悪は「親のせい」・・・(^^;
いい加減にせい!
ありがとうございました。
いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、
https://imcfujimoto.net/
いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。
興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!
https://imcfujimoto.net/free/school